防災士に興味を持ったものの、防災士の難易度について不安を感じていませんか?実際にネット上でも知恵袋をはじめとした掲示板では、「合格率は高いらしいけど本当に簡単なの?」「勉強時間はどれくらい必要?」といった声が多く見られます。
また、防災士は役に立たないという否定的な意見や、試験に落ちた人はいるのかといったリアルな体験談も気になるところでしょう。
この記事では、「防災士とは」どのような資格なのかという基本情報から始まり、防災士の資格の取り方、試験日や費用、勉強方法や過去問の活用方法まで幅広く解説します。
さらに、資格取得のメリットや注意点も詳しく紹介することで、防災士を目指すあなたが後悔なく準備を進められるようサポートします。
防災士の難易度の実態を正しく知ることで、迷いや不安を解消し、自信を持って次の一歩を踏み出しましょう。
■本記事のポイント
- 防災士の試験難易度と実際の合格率の関係
- 資格取得までの流れと必要なステップ
- 勉強時間や試験対策の具体的な方法
- 防災士資格のメリットや活用シーン
防災士の難易度はどれくらいなのか?
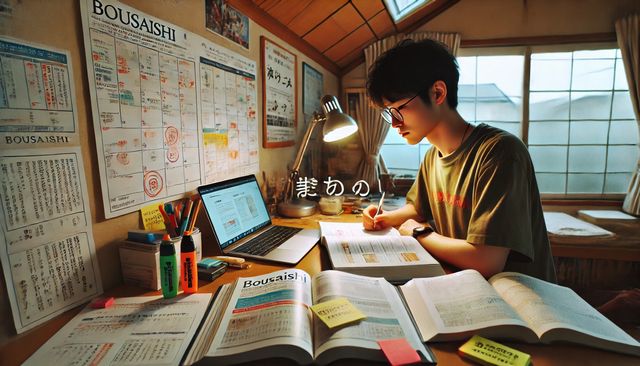
防災士に興味があるものの、「難易度は高いのでは?」と不安を感じていませんか?実は防災士の資格は、しっかりとポイントを押さえれば決して難しいものではありません。
ただし、合格率の高さだけを見て油断してしまうと、思わぬ落とし穴にはまる可能性もあります。
ここでは、防災士試験の実際の合格率と難易度の関係、勉強時間の目安、そして「試験に落ちる人はいるのか?」という気になるポイントを詳しく解説します。
資格取得を目指すうえで、まず知っておきたい現実を見ていきましょう。
どんな資格なのか解説
防災士とは、地震や台風などの自然災害に備えるための「防災力」を身につけた人に与えられる民間資格です。
国家資格ではないものの、その重要性から多くの自治体や企業、地域団体が取得を推奨している注目の資格です。
この資格の最大の特徴は、「自助・共助・協働」という3つの理念を基盤としている点です。
自助とは自分の命を自分で守る力、共助とは地域や職場でお互いを支え合うこと、そして協働は市民・企業・行政などが連携して防災活動を行うことを指します。
防災士はこれらの考え方を実践するリーダーとして、地域社会の安全を支える存在として期待されています。
一方で、防災士の資格を持っているからといって、法律的な権限や義務があるわけではありません。
あくまでも個人が防災に対する知識と意識を高め、災害発生時や平常時に正しい行動が取れるように備えるための資格です。
例えば、災害時には避難誘導や避難所の運営サポートを行うこともありますし、平常時には防災訓練の指導や地域への啓発活動に携わるケースもあります。
このように、防災士は知識だけでなく、地域貢献意識の高い人が取得することで真価を発揮する資格だといえるでしょう。
防災に対して関心がある方にとって、非常に実用的で意味のある資格です。
資格の取り方とステップ

防災士になるためには、決められた3つのステップをすべてクリアする必要があります。
試験に合格するだけではなく、講習や実技を含む実践的な流れが特徴です。
まず第一のステップが「防災士養成研修講座」の受講です。
この講座では、防災士教本に基づいた専門的な知識を学びます。
内容は多岐にわたり、災害の種類ごとの対策や避難誘導、地域との連携方法などが含まれています。
講座を修了すると「研修履修証明」が発行され、次の試験への受験資格が得られます。
次に「防災士資格取得試験」を受けることになります。
三択式の筆記試験で、全30問中24問(80%)以上の正答で合格となります。
この試験は、講座の最終日に会場で行われることが一般的です。
しっかりと講義を聞き、教本を読み込んでいれば、特別な予備知識がなくても対応できる難易度といえます。
そして最後に、「救急救命講習」の受講が必要です。
これは消防署や赤十字社などが実施している講習で、心肺蘇生法やAEDの使用方法など、緊急時の応急処置に関する内容が3時間以上にわたって行われます。
修了証は5年以内の発行かつ有効期限内であることが条件となるため、取得のタイミングには注意が必要です。
この3つの手順を完了すると、日本防災士機構に「防災士認証登録申請」を行うことができ、正式に防災士として認められます。
単に知識を得るだけでなく、実践を重視した流れになっている点が防災士資格の特徴といえるでしょう。
試験日や費用を確認しよう
防災士の資格を取得するにあたって、気になるのが試験のスケジュールと費用です。
受講を検討している方は、あらかじめ全体の流れと必要経費を把握しておくことが大切です。
まず試験についてですが、防災士資格取得試験は基本的に「防災士養成研修講座」の最終日に、研修会場で行われます。
したがって、全国一斉の日程があるわけではなく、講座の実施機関や地域によって異なる開催スケジュールに基づいて行われます。
年間を通じて複数回開催されているため、自分の都合に合わせて受講日程を選ぶことが可能です。
費用に関しては、受講機関や講習の内容によって異なりますが、基本的な内訳は以下の通りです。
・防災士教本代:約3,500円から4,000円
・防災士資格取得試験受験料:3,000円(非課税)
・防災士認証登録料:5,000円(非課税)
・防災士養成研修講座受講料:約49,000円から53,900円
これらを合計すると、一般的なケースでおおよそ60,000円前後が必要になります。
ただし、自治体主催の研修に参加する場合は助成金や学割制度などが適用され、費用を大幅に抑えられることがあります。
警察官や消防関係者、赤十字救急員などに向けた特例制度も存在しており、受講料の減額や一部免除が適用されることもあります。
このように、試験の日程は研修スケジュールに準じ、費用もケースによって大きく異なります。
受講を決める前に、地域の講座情報や割引制度についてしっかり確認しておくことが大切です。
費用面でのハードルを感じている場合も、工夫次第で負担を軽減できる可能性があるため、情報収集は念入りに行いましょう。
合格率と難易度の関係性

防災士の試験は「難易度が高い資格ではない」と言われていますが、その背景には合格率の高さがあります。
実際、日本防災士機構が公表している直近の合格率は90%を超えており、多くの受験者が合格していることが分かります。
特に2023年度の合格率は92%とされており、非常に高水準です。
このような数値を見ると、簡単に合格できる印象を受けるかもしれません。
しかし、これは防災士の試験が単なるペーパーテストではなく、講座の受講や自宅学習を通して、あらかじめ知識を身につけてから受ける構成になっているためです。
つまり、試験自体の難易度は比較的低くても、しっかりと準備して臨む必要があることに変わりはありません。
試験は30問の三択問題で、24問以上正解すれば合格という設定です。
設問の多くは、防災士教本から出題されるため、教本をしっかり読み込んでおけば十分に対応できます。
ただし、研修中の内容に集中できなかったり、教本を読み流してしまうと、思わぬところでつまずくこともあるでしょう。
このように見ていくと、「合格率が高い=簡単に取れる」とは言い切れません。
合格するためには、最低限の学習と理解が求められます。
高い合格率の裏には、講座の充実度や学習サポートの存在があるという点を意識しておくことが大切です。
勉強時間はどのくらい必要?
防災士の試験に合格するための勉強時間は、個人差があるものの一般的には10から20時間ほどが目安とされています。
これは、防災士の試験が三択式で、なおかつ出題範囲が防災士教本に限定されていることから、集中して取り組めば比較的短時間で要点を押さえられる構成になっているためです。
ただ、研修講座の事前に提出する「履修確認レポート」には数百問に及ぶ設問があり、単なる丸写しではなく、内容を理解しながら進める必要があります。
教本の分量はかなり多く、初めて読む場合は通読するだけでも5から10時間ほどかかる可能性があります。
そこから理解を深めたり、復習を含めた勉強を加えると、やはり20時間前後の準備が理想的です。
さらに、試験対策用の問題集や模擬試験が手元にある場合、それを繰り返し解くことで理解度は格段に上がります。
過去問のような形式に慣れることで、本番でも冷静に問題を処理できるようになるため、演習時間も含めてスケジューリングしておきたいところです。
一方で、時間に余裕がない方や勉強が苦手な方は、早めの準備を始めることが重要です。
毎日30分程度でも積み重ねれば、2から3週間で必要な内容を網羅することができます。
このように、自分の生活スタイルや集中力に合わせて、計画的に勉強時間を確保することが、防災士資格取得のカギになります。
試験に落ちた人はいるのか?

合格率が高い防災士試験ですが、実際には「落ちた」というケースも一定数存在しています。
これは珍しいことではなく、受験した人すべてが合格しているわけではないという点に注意が必要です。
試験に不合格となる理由の多くは、「事前学習が不十分だった」「教本を十分に読み込めていなかった」「出題形式に慣れていなかった」などが挙げられます。
とくに、講座を受講した安心感から復習を怠ったり、履修確認レポートを丸写しで済ませてしまった人ほど、試験で苦戦する傾向が見られます。
さらに、研修当日は長時間の講義とスケジュールのタイトさもあって、集中力を保つのが難しくなることもあります。
加えて、三択とはいえ問題文の読解力や細かな内容の記憶も問われるため、うろ覚えでは通用しません。
ただし、防災士の試験には再受験制度があり、試験だけをもう一度受け直すことが可能です。
再受験にあたっては追加費用が発生しない場合もあるため、研修機関や日本防災士機構に確認してみると良いでしょう。
このように、油断すれば不合格になることもありますが、しっかり準備すれば誰にでも合格のチャンスがある試験です。
試験に落ちたとしても諦める必要はありません。
次に向けて学び直しをする姿勢こそが、防災士としての資質を高める第一歩になるのではないでしょうか。
防災士の難易度とリアルな受験事情
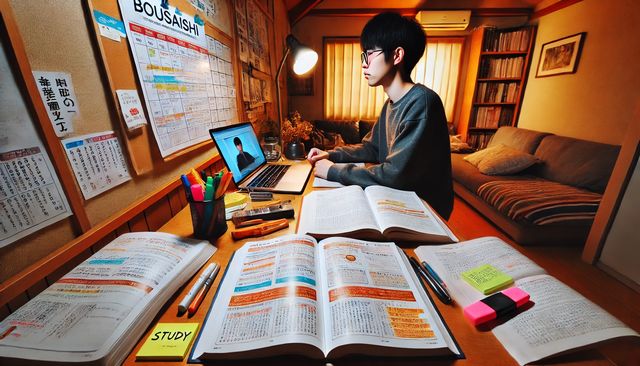
防災士の資格は「誰でも受けられる」といわれる一方で、実際にどれほどの人が学び、試験を受け、活用しているのでしょうか。
ここでは、合格率の数字から見える試験の実態や、勉強にかけるべき時間、そして「落ちることはあるのか?」というリアルな疑問にフォーカスします。
ネット上の噂や口コミとは異なる、正確で信頼できる情報をもとに、防災士受験の現実を紐解いていきましょう。
防災士は役に立たないって本当?
防災士の資格について、「役に立たないのでは?」という意見を耳にすることがあります。
しかし、この疑問には少し誤解も含まれているようです。
たしかに、防災士は就職や昇給に直接つながる国家資格ではなく、職業的な特典が多いわけではありません。
そのため、資格単体で「仕事に有利になる」ことを期待して取得する人にとっては、思ったよりも効果を感じられないことがあるのも事実です。
一方で、防災士は災害時におけるリーダーシップを発揮したり、平常時から地域や職場の防災意識を高めたりすることが求められる資格です。
特に地震・台風・水害などが頻発する日本では、自助・共助・協働の知識と行動力が社会全体で必要とされています。
実際に、地域防災訓練や避難所運営、学校や企業での防災教育に携わる場面では、防災士の知識が大きく役立っています。
このように、「役に立つかどうか」は活かし方次第です。
ただ持っているだけでは意味が薄れてしまう資格ですが、地域貢献や家庭・職場の安全対策などに積極的に使えば、防災士は非常に実用性の高い資格だといえるでしょう。
知恵袋でも話題の資格

防災士に関する疑問や体験談は、Yahoo!知恵袋やSNSなどの投稿でも多く見られます。
それだけ多くの人が関心を持っている資格であるといえます。
検索してみると、「防災士って意味あるの?」「試験難しいですか?」といったリアルな質問が投稿されており、防災士が一般的にも注目されている存在であることが分かります。
知恵袋の書き込みからは、防災士に対して期待している人だけでなく、不安や疑問を持っている人の声も多く拾うことができます。
例えば「受講料が高いけど元が取れるのか」「仕事に活かせるのか」といった現実的な悩みは、資格選びの参考になります。
一方で、「地域活動に役立った」「家族で防災意識を高められた」といったポジティブな体験談も多く見受けられます。
特に大規模災害が起きた年には、防災士への関心が一気に高まる傾向があり、そのたびに知恵袋でも議論が活発になります。
このように、知恵袋などのユーザー投稿は、防災士の実態や活用法を知る上での貴重な情報源です。
これから資格取得を検討している方は、実際の声に目を通してみると、よりリアルな判断材料が得られるでしょう。
試験対策に過去問は使える?
防災士試験の対策において、過去問は非常に有効な学習ツールです。
なぜなら、防災士試験の問題は基本的に毎年大きく変更されるわけではなく、防災士教本に準拠した内容から繰り返し出題される傾向があるからです。
実際、市販の問題集では「過去問題に近い内容」や「傾向を反映した模擬問題」が多数収録されており、それらを活用することで効率的な学習が可能になります。
ただし、防災士の試験問題は正式な過去問として公開されていません。
そのため、書店などで販売されている「非公式の過去問集」や、受験経験者がまとめた問題形式に基づいた教材を使うことになります。
これらは完全一致ではないものの、実際の試験形式や出題傾向を理解するには十分な内容です。
特に初めて受験する方にとっては、三択形式に慣れておくことが重要です。
模擬問題を繰り返し解くことで、設問のパターンや選択肢のひねり方に慣れることができるため、緊張せずに本番に臨むことができます。
また、防災士研修センターなどの講座を受ける場合、試験対策ブックが配布されることもあります。
これも過去問に近い内容で構成されており、対策に有効です。
つまり、公式の過去問がないとはいえ、対策方法はしっかりと用意されているということです。
勉強の際には、テキストだけでなく問題演習も並行して取り入れることをおすすめします。
資格取得にあるメリット

防災士の資格は、災害時だけでなく日常生活の中でも幅広く活かせる実用性の高い資格です。
まず大きなメリットとして、自分や家族の命を守るための知識や行動力を身につけることができます。
地震や水害などの自然災害が多発する日本において、防災への備えは誰にとっても必要不可欠です。
防災士として学ぶ内容は、非常時の初動対応や避難行動に直結するものであり、知識を持っているかどうかで行動に差が出ます。
また、地域や職場で防災意識を広める存在としても、防災士の資格は重宝されます。
特に自治体主催の防災訓練や学校・企業での啓発活動では、防災士の資格があることでリーダー的な役割を任されることも少なくありません。
名刺や履歴書に記載できるため、防災への意識が高い人材として信頼感を与えることもできます。
もう一つのメリットは、資格自体が一度取得すれば更新が不要な「終身資格」である点です。
再講習などの義務もなく、一生涯にわたって防災士として活動できます。
そのため、長期的な自己投資としてもコストパフォーマンスが高い資格だと言えるでしょう。
ただし、資格取得そのものに経済的なリターンを期待するのは難しいため、収入アップを目的とする方には向かないかもしれません。
あくまで自助・共助・協働を意識し、災害時に冷静に行動できる人材になることが最大の利点です。
勉強を続けるコツと注意点
防災士の勉強を継続するには、「目的意識」と「計画性」の両方が重要です。
資格試験は一度きりの合格で終わるかもしれませんが、本当の意味で防災士として活躍するには、その後も継続して知識をアップデートしていく必要があります。
防災に関する制度や災害の傾向は年々変化しており、過去の情報にとらわれすぎると実際の現場で対応が遅れることにもなりかねません。
まず、勉強を続けるモチベーションを保つには、「誰のために防災士としての知識を活かしたいのか」を明確にしておくと効果的です。
家族を守りたい、地域に貢献したい、職場の安全を高めたい、そうした目的があれば、自然と学習を続ける意味も見えてきます。
また、継続的な勉強にはスケジュール管理も欠かせません。
すべてを完璧に学ぼうとすると途中で挫折しやすいため、教本を少しずつ読み返す、ニュースから防災情報を得る、定期的に防災訓練に参加するなど、日常の中で防災意識を保つ工夫を取り入れるとよいでしょう。
注意点としては、「資格を取ったら終わり」と思い込まないことです。
資格があることよりも、それをどう使うかが本質です。
また、ネット情報やSNSだけに頼らず、必ず公式な防災士教本や自治体の情報をベースに学ぶようにしてください。
間違った情報を広めてしまうと、かえって混乱を招くリスクがあります。
防災士は誰に向いている資格なのか

防災士は、特定の職業に限定される資格ではなく、あらゆる立場の人に門戸が開かれています。
年齢や職種、学歴を問わず誰でも受験が可能であり、「人の命を守る」という共通の目的を持つすべての人に価値のある資格といえるでしょう。
特に向いているのは、地域活動に関心のある方や、家族の安全を最優先に考える家庭の主婦・主夫、学校や保育園など子どもに関わる現場で働く方々です。
こうした人たちは、いざという時に周囲の命を守るための知識や判断力が求められるため、防災士の知識が役立ちます。
また、企業においても、ビル管理、警備、施設運営、建築・土木関係など、安全管理に携わる職種の方には特におすすめです。
資格を持っていることで、社内の防災マニュアル作成や研修の場でも活躍の場が広がることがあります。
反対に、「資格を取ったら何か仕事に直結する」といった経済的なリターンを重視する人にはあまり向いていないかもしれません。
防災士は利益を目的にする資格ではなく、社会貢献や防災意識の向上を目的にした活動が中心です。
このように、防災士は「人を守りたい」「社会の役に立ちたい」という思いがある人にこそ向いている資格です。
特別なスキルや知識がなくても、正しい意識と学ぶ意欲があれば、誰でも目指すことができます。
【まとめ】防災士の難易度を総括
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。


