電気通信主任技術者の難易度は実際どの程度なのか、気になっている方は多いのではないでしょうか。
電気通信主任技術者の難易度で検索する人の多くは、他資格との比較や合格までに必要な勉強時間、過去問の有効性、さらには科目別の対策方法などを具体的に知りたいと考えているはずです。
この記事では、国家資格としての電気通信主任技術者を、ランキングや偏差値といった客観的な指標を用いて整理しながら、「電気主任技術者」や「一陸技」との比較、工事担任者と電気通信主任技術者との違いについてもわかりやすく解説します。
また、伝送交換と線路のどちらが難しいのか、役に立たないという声の真相、逆に「すごい」と評価される理由、科目免除や裏ワザ的な勉強法など、実践的な情報も盛り込みました。
資格取得後に「できること」についても触れているため、電気通信主任技術者を目指す価値があるかどうか判断する材料として、ぜひ最後までご覧ください。
■本記事のポイント
- 他の国家資格と比較した難易度の位置づけ
- 試験科目ごとの難易度の違いと対策ポイント
- 合格率や勉強時間の目安と合格への工夫
- 資格取得後にできる業務や活用シーン
電気通信主任技術者の難易度はどれくらい?
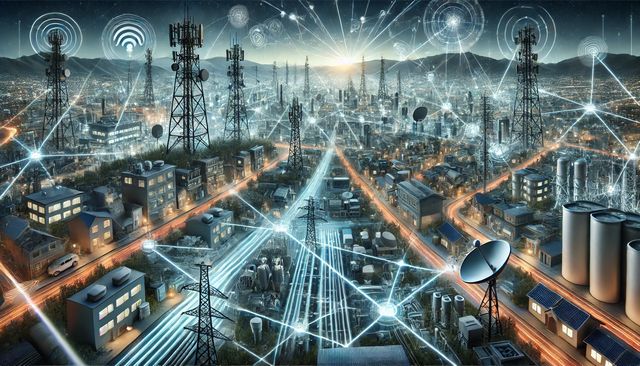
電気通信主任技術者の難易度は、国家資格の中でも「中級以上」とされるやや難関な部類に入ります。
ただし、単に難しいと一言で片付けられるものではなく、比較対象や自身のバックグラウンドによってその体感は大きく変わります。
そこでここでは、他の資格との比較や偏差値、業務範囲の違いなど、客観的かつ実務的な視点から難易度を深掘りしていきます。
試験に挑戦する価値があるのか、自分にとってどのくらいの準備が必要なのか、読み進める中で見えてくるはずです。
資格ランキングから見る難易度の位置づけ
電気通信主任技術者は、国家資格の中でも中堅からやや難関のレベルに位置づけられる資格です。
特に、IT系や通信系の技術者向け資格の中では、一定の知識と実務的な応用力が求められるため、難易度は決して低くありません。
通信・インフラ分野における資格ランキングでは、たとえば「工事担任者」や「第二種電気工事士」などの入門から初級レベルの資格と比較して、電気通信主任技術者はより専門性が高く、難易度も一段上に設定されています。
一方、「第一級陸上無線技術士(一陸技)」や「電気主任技術者(電験)」などの上級資格よりはやや低めに見られることが一般的です。
このようなランキングでは、合格率や出題範囲の広さ、業務独占性、社会的評価などが総合的に評価されます。
電気通信主任技術者の合格率は20から30%台で推移しており、簡単に合格できる試験ではありません。
特に伝送交換の区分では受験者数も多く、平均的な合格率はやや低めです。
そのため、電気通信主任技術者は、資格取得でキャリアアップを目指す中級から上級レベルの技術者にとって、有力な選択肢の一つといえるでしょう。
通信インフラの設計・監督に携わる人材としての証明にもなるため、現場経験がある人にとっては実務と結びつきやすいという強みもあります。
偏差値で比較する国家資格の中の位置

国家資格の難易度を偏差値で表す場合、電気通信主任技術者は偏差値55から60程度に位置づけられることが多いです。
これは、国家資格全体の中では中間よりもやや難しい部類に入り、専門的知識を持つ人でなければ合格が難しい試験であることを示しています。
偏差値を使って資格を分類する手法では、合格率の他に出題範囲の広さや試験内容の専門性、必要な学習時間なども評価対象となります。
電気通信主任技術者試験は、「法規」「電気通信システム」「伝送交換または線路設備及び設備管理」といった複数の分野にまたがり、それぞれに独立した専門知識が求められます。
たとえば、偏差値65を超えるような資格には、「一級建築士」や「司法書士」「電験一種」などがありますが、電気通信主任技術者はそれより一段階下。
逆に、「危険物取扱者乙種」や「第二種電気工事士」などと比べれば、遥かに難易度は高く設定されています。
このように、偏差値ベースでも電気通信主任技術者は技術系資格の中では中堅から上級に位置する実力派資格であり、計画的な学習が必要不可欠です。
電気通信主任技術者と電気主任技術者の違い
電気通信主任技術者と電気主任技術者は、似た名称ながら担当する設備や役割が大きく異なります。
どちらも国家資格であり、インフラを支える重要なポジションにありますが、その専門分野には明確な違いがあります。
電気主任技術者は、電力を扱う設備の保安監督を行う資格で、「電験」という略称でも知られています。
発電所、変電所、工場などに設置された高圧電気設備の安全管理を担い、電気エネルギーの供給側に位置する役割です。
資格は一種から三種まであり、合格率は10%未満になることもある難関資格です。
一方、電気通信主任技術者は、通信ネットワークやインターネットなどの「情報通信インフラ」を管理・監督する資格です。
電気通信設備に関する工事、維持、運用の技術的責任を負う立場で、伝送交換と線路という2つの専門区分があります。
つまり、電気主任技術者は「電力インフラの監督者」、電気通信主任技術者は「通信インフラの監督者」という違いがあります。
扱う対象が電気か通信かという点で大きく分かれ、業務内容、必要な知識、法的義務の内容も異なります。
業務範囲や求められる技術の方向性が違うため、どちらの資格を目指すべきかは、自分のキャリアや携わりたい分野に合わせて検討するとよいでしょう。
一陸技と電気通信主任技術者の難易度比較

一陸技(第一級陸上無線技術士)と電気通信主任技術者の難易度を比較すると、一陸技のほうが一般的に難易度が高いとされています。
一陸技は、総務省が定める無線技術の国家資格で、無線通信設備に関する設計・管理・保守などに必要な知識と技術を認定するものです。
この資格は特に放送局や航空無線、海上無線の分野で重要視されており、試験範囲は物理・電気回路・電子回路・無線工学・法規など多岐にわたります。
計算問題も多く、理系出身者でも高い学習負荷を感じる内容になっているのが特徴です。
一方、電気通信主任技術者は、より「有線のネットワーク設備」や「設備の運用管理」に焦点を当てているため、実務に近い知識が求められる傾向があります。
法規やセキュリティ管理など、マネジメント的な視点も含まれるため、現場経験があると有利に働く場合もあります。
つまり、一陸技はよりアカデミックで理論的な難しさがあるのに対し、電気通信主任技術者は現場対応や運用に即した実務的な内容が中心です。
学習スタイルやバックグラウンドにより、どちらが難しいと感じるかは変わりますが、単純な出題範囲の広さや合格率の低さでは、一陸技のほうがやや上と言えるでしょう。
ただし、いずれの資格も高い専門性を持ち、取得によってキャリアの幅が広がる点では共通しています。
どちらを目指すにしても、継続的かつ計画的な学習が必要です。
工事担任者と電気通信主任技術者の差は?
工事担任者と電気通信主任技術者は、いずれも電気通信に関わる国家資格ですが、業務範囲や求められる知識、社会的な位置づけに明確な違いがあります。
まず工事担任者は、電話機やインターネット回線といった「端末設備」に関する工事や接続の監督を行うための資格です。
いわば、建物の内部や個人宅などにおける通信機器との接続に関する責任者です。
資格のレベルも複数あり、AI種、DD種などの種類に分かれています。
受験のハードルも比較的低く、基本的な通信知識を中心に問われます。
一方、電気通信主任技術者は、事業用の通信ネットワーク全体、つまり大規模な電気通信設備の工事や維持・運用の監督を行う役職を担うための資格です。
対象範囲が工事担任者よりも遥かに広く、企業や公共機関の通信インフラ全体を支える立場となるため、より高度な知識と責任が求められます。
また、法的な位置づけも異なります。
電気通信事業法では、一定規模の電気通信事業者には電気通信主任技術者の配置が義務付けられており、単なる資格というだけでなく、「選任」が必要な重要なポジションとされています。
このように、工事担任者は実務寄りの施工資格、電気通信主任技術者はマネジメントと運用管理を含む上位資格と考えると、両者の役割の違いが見えてくるでしょう。
将来的に通信業界でのキャリアアップを目指す場合は、工事担任者を取得した後に、電気通信主任技術者にステップアップする流れが一般的です。
合格に必要な勉強時間の目安とは

電気通信主任技術者試験に合格するためには、計画的な学習時間の確保が不可欠です。
試験範囲が広く、専門性の高い内容が多いため、短期集中型の学習だけでは合格が難しいケースもあります。
勉強時間の目安としては、3科目を受験する場合であれば、一般的に300から400時間程度が必要とされます。
これは週10から15時間の学習を継続した場合、3から6ヶ月ほどの学習期間を要する計算になります。
ただし、これはあくまで平均的な目安であり、個々の基礎知識や経験値によって大きく変動します。
例えば、すでに工事担任者や関連分野の知識がある人であれば、学習効率が高まり必要時間も短縮できます。
一方で、初学者が一から取り組む場合は、500時間以上かかることも珍しくありません。
また、電気通信主任技術者試験では法改正の反映や計算問題への対応なども必要であるため、単なる暗記だけでなく「理解に基づいた知識定着」が求められます。
この点を考慮すると、毎日の積み重ねと反復学習が大きな鍵を握ります。
学習を始める前には、まず自身の生活スタイルや業務スケジュールを確認し、現実的に確保できる勉強時間を洗い出してから、無理のないスケジュールを立てることが重要です。
中長期的な視点で取り組むことが、最終的な合格率の向上につながります。
合格率を上げる裏ワザ的な工夫とは?
電気通信主任技術者試験において、ただ闇雲に勉強するのではなく、合格率を高めるための工夫を取り入れることで、より効率的に結果を出すことが可能です。
いわゆる「裏ワザ」とも言えるテクニックには、いくつかの共通パターンがあります。
まず有効なのが「科目免除制度」の活用です。
この試験では過去に合格した科目が3年間有効となるため、一度にすべての科目をクリアしなくてもよいという特徴があります。
そのため、1回の試験で1科目ずつ確実に合格していく戦略を取る人も多く、結果的にプレッシャーが減り、着実に資格取得へと近づけます。
次に、合格者が口を揃えて勧めるのが「過去問学習の徹底」です。
過去問から出題傾向や時間配分のコツを掴むことで、本番の試験にも落ち着いて対応できるようになります。
特に選択肢の文言や問題のクセに慣れておくことは、マークシート方式の試験では大きなアドバンテージになります。
さらに、学習効率を上げる方法としては「朝学習の習慣化」が挙げられます。
朝は脳がリフレッシュされた状態であり、記憶の定着にも効果的です。
毎朝30分でも学習にあてることで、継続性と集中力を両立できます。
これらの工夫は、いずれも「限られた時間で合格を目指す」ための具体的な手段です。
ただし、裏ワザ的な方法だけに頼るのではなく、自分のペースと理解力を見極めながら活用することが大切です。
効率化と基礎力のバランスが、合格への最短ルートになるでしょう。
電気通信主任技術者の難易度の攻略ポイント

電気通信主任技術者試験は、出題範囲の広さや専門性の高さから難易度が高めとされる試験です。
しかし、正しい対策を講じることで、誰でも十分に合格を目指せます。
ここでは、限られた時間の中で効率よく学習を進めるための実践的なポイントをご紹介します。
過去問の活用法から、科目免除制度の使い方、さらに合格後に広がる可能性まで、合格に近づくための具体的なヒントを一つずつ見ていきましょう。
科目別で見る難易度の違い
電気通信主任技術者試験では、「法規」「電気通信システム」「伝送交換設備および設備管理」「線路設備および設備管理」の4科目がありますが、受験区分によって科目が一部異なります。
具体的には、「伝送交換主任技術者」は伝送交換設備を、「線路主任技術者」は線路設備を選択することになります。
これらの科目の中で最も取り組みやすいとされているのが「法規」です。
理由は出題内容の多くが法令に基づいた暗記問題で構成されており、他の科目に比べて計算や実務的な応用が少ないためです。
ただし、法改正が頻繁に行われるため、常に最新の情報を取り入れる必要があります。
一方、「電気通信システム」は工学的な内容が含まれ、計算問題や技術的な知識が問われるため、理系出身でない人にとってはやや難易度が高く感じられることもあるでしょう。
加えて、この科目は理解力が問われる部分が多く、表面的な暗記だけでは対応しきれないという特徴があります。
最も難易度が高いとされるのは、「伝送交換設備」や「線路設備」の専門科目です。
これらは業務経験がないとイメージしにくい実務的な内容が多く、セキュリティやソフトウェア管理、設備の構造といった具体的な知識が求められます。
受験者の中でも、これらの専門科目でつまずく人が多い傾向にあります。
つまり、科目ごとに求められる能力や対策の方向性が異なるため、自分の強みや学習スタイルに合わせた戦略的なアプローチが重要です。
線路と伝送交換のどちらが難しい?

「線路」と「伝送交換」は、電気通信主任技術者試験の二大区分です。
どちらを選ぶべきか悩む人も多いのですが、難易度には明確な違いがあります。
過去の合格率の推移を見ると、「線路主任技術者」の方が「伝送交換主任技術者」よりも合格率が高く、受験者数も少ないため、相対的に見ると線路の方がやや取り組みやすいとされています。
これは出題内容が比較的限定的で、設問に応じた対策が立てやすいことが一因と考えられます。
一方で、「伝送交換」は通信の中核を成す分野だけに、出題範囲が広く、システムやソフトウェア、設備構成など、より高度な知識が問われる傾向にあります。
計算や理論的な問題も含まれるため、初学者には難しく感じられることが多いです。
ただし、実務経験や業務での関わりがある人にとっては、どちらの区分でも学習が進めやすくなります。
特に現場経験がある場合は、伝送交換でも線路でも対応できる可能性が高いでしょう。
つまり、どちらが難しいかは受験者のバックグラウンドにもよりますが、初学者や文系出身者にとっては、線路のほうがややハードルが低く感じられる傾向があります。
「役に立たない」って本当?評価を検証
電気通信主任技術者について「役に立たない」といった声があるのは事実ですが、それは資格の活用方法や所属業界によって評価が分かれるためです。
この資格は、あくまで「一定規模の電気通信事業者における技術責任者を配置するための法定資格」として位置づけられており、一般的な転職市場や全業種に通用するような「万能資格」ではありません。
そのため、通信事業者やインフラ系企業に属していない場合、実感として活かす場面が少ないことから、評価が低くなることもあるのです。
ただし、対象となる業界においては、その価値は高く、法的に必要とされる資格であるため、資格手当が付与されたり、昇進・選任要件に直結するケースも多く見られます。
特にネットワークインフラが発展している現在、5GやIoTの導入が進む中で、この資格の価値は再評価されつつあります。
つまり「役に立たない」と感じるのは、その人の職場環境やキャリアパスと噛み合っていない場合が多く、資格そのものが無価値であるというわけではありません。
業界を選べば、むしろ非常に強力な武器になる資格です。
「すごい」と言われる理由とは?

電気通信主任技術者が「すごい」と言われるのは、その資格が持つ社会的な役割と責任の重さにあります。
国家資格であることに加え、電気通信事業法に基づき、一定規模以上の通信事業者には有資格者の選任が義務付けられているため、法律上必要とされる存在なのです。
さらに、扱う対象が一般家庭レベルの通信設備ではなく、企業や自治体、通信インフラ全体に及ぶ設備である点も特筆すべきポイントです。
つまり、国家レベルの通信網を支える存在であり、その業務内容には設計・施工管理・保守・運用といった全工程が含まれます。
また、この資格を持つことで、ネットワーク管理における技術力や法規対応力があることを証明できるため、キャリアアップや社内での昇格、外部企業への転職時にも高く評価される傾向にあります。
こうした背景から、業界内では「すごい」と言われることが多く、名刺に記載することで信頼度が増す資格の一つでもあります。
地味ではありますが、社会的信用と実務能力を兼ね備えた技術者としての証明になる点が、この資格の大きな魅力と言えるでしょう。
過去問を活用した効果的な対策法
電気通信主任技術者試験の学習において、過去問を使った対策は最も効率的な方法の一つです。
単に問題を解くだけでなく、出題傾向を分析し、自分の弱点を把握していくための「教材」として活用することがポイントになります。
まず最初に行うべきなのは、過去3から5年分の試験問題に一通り目を通すことです。
これにより、どの科目にどのような傾向があるのか、繰り返し出題されているテーマは何かをつかむことができます。
特に「法規」では似たような条文や項目が何度も問われる傾向があり、正確な暗記と理解が得点に直結します。
一方、「電気通信システム」や「伝送交換・線路設備」に関しては、応用問題や計算問題も多く、単純な丸暗記では対応しきれない場面があります。
このような科目では、過去問を解いたあとに必ず解説を読み、自分なりに「なぜその選択肢が正解なのか」を言語化する習慣をつけましょう。
また、時間を測りながら模擬試験として過去問を使うのも有効です。
本番の時間配分に慣れておくことで、試験当日の緊張感を和らげる効果もあります。
反復演習を重ねることで、自然と出題形式にも慣れ、思考スピードが上がっていきます。
過去問の活用は、単なる反復ではなく「質の高い復習と分析」を通じて知識を定着させていく作業です。
自分のミスや理解不足に目を向け、修正を繰り返すことで、合格に近づくことができるでしょう。
科目免除制度を上手に使う方法

電気通信主任技術者試験には、他資格の取得や過去の合格実績、学歴・実務経験に基づいて試験科目を一部免除できる制度が用意されています。
この制度を活用すれば、学習量や試験負担を大きく減らせるため、戦略的に使うことが重要です。
免除対象となるのは主に「電気通信システム」や「法規」などで、たとえば「工事担任者」や「陸上無線技術士」といった関連資格を持っている場合、その知識が評価されて該当科目が免除される可能性があります。
また、以前に合格した科目は3年間の有効期間があり、その間は再受験が不要となります。
制度を活用するためには、受験申し込み時に免除申請を行い、必要な証明書類(資格証明書、修了証明書など)を提出する必要があります。
申請が認められると、受験票に免除された科目が表示される仕組みになっています。
ここで注意したいのは、免除されたからといって「完全に学習を省いてよい」というわけではない点です。
実務で必要になる知識も含まれているため、可能であれば簡単に復習しておくことをおすすめします。
つまり、科目免除制度はうまく使えば大きなアドバンテージになりますが、手続きや要件の確認が必要です。
試験要項や協会の公式サイトで最新情報をしっかりチェックし、自分が該当するかどうか早めに把握しておくようにしましょう。
電気通信主任技術者でできること一覧
電気通信主任技術者の資格を取得すると、電気通信分野におけるさまざまな技術的・管理的な業務に従事できるようになります。
この資格は単なる知識証明ではなく、法令上の「選任義務」が課せられる業務に就くための前提資格でもあります。
主にできることとしては、事業用電気通信設備の工事・保守・運用に関する監督業務があります。
これには、光ファイバーや通信ケーブルの敷設から、伝送交換設備やルーター・スイッチなどの通信機器の設定・管理、セキュリティ対策までが含まれます。
さらに、一定規模以上の通信事業者においては、電気通信主任技術者を法的に配置しなければならないことが定められています。
そのため、有資格者であることが昇進や重要ポストへの登用条件になることも珍しくありません。
また、企業によってはこの資格が「主任技術者選任条件」となることから、監理技術者や工事管理者として現場の責任を担うことも可能です。
通信系の建設業者においても、建築工事やネットワークインフラ工事の監督者として活躍する道が開けます。
加えて、資格手当や転職・再就職での優遇など、キャリア上のメリットも多数あります。
特に5GやIoT、クラウド基盤の普及が進む中で、インフラ整備を担える人材のニーズは年々高まっており、この資格の価値も同時に高まっているのが現状です。
このように、電気通信主任技術者は「できること」が明確かつ広範囲にわたり、通信インフラを支える専門職としての社会的意義も非常に大きい資格だといえます。
【まとめ】電気通信主任技術者の難易度を総括
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。


