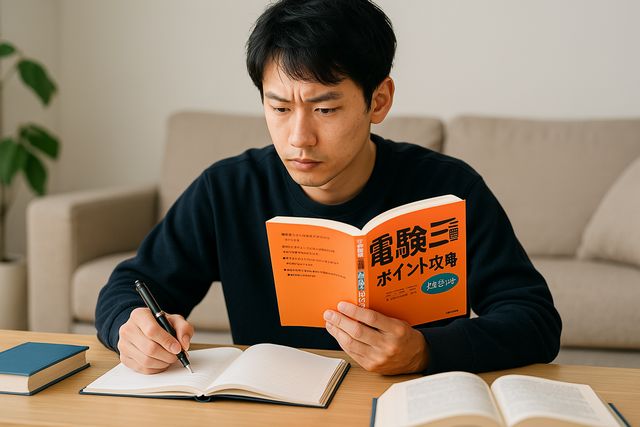電験三種の難易度wp大学でいうとと検索している方の多くは、この資格の難しさを大学入試レベルでイメージしたいと考えているのではないでしょうか。
電験三種は、電気主任技術者としての資格であり、取得すればインフラや製造業界で高い評価を得られる国家資格です。
その反面、合格率が低い理由や出題範囲の広さから、独学では難しいと感じる人も多い試験です。
この記事では、電験三種の難易度ランキングにおける位置づけや、最近難易度が下がったと言われている背景を解説します。
また、国立大学とのレベル感を比較し、現役合格できる大学の目安や大学生におすすめの理由についても具体的に紹介します。
さらに、学生バイトとの両立が可能かどうか、他資格との難易度比較、さらには役に立たないと誤解されがちな実態にも触れます。
年収アップやキャリア形成の武器として、どれだけ「すごい」資格なのかを、データと事例をもとに分かりやすくお伝えします。
資格選びに迷っている方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
■本記事のポイント
- 電験三種の難易度が大学入試でいうとどのレベルに相当するか
- 難易度が高い理由や合格率が低い背景
- どの大学に在籍していれば現役合格が狙えるか
- 電験三種取得によって得られる将来のメリットや年収の目安
電験三種の難易度を大学でいうと中堅私大レベル?

電験三種は「難関国家資格」として知られていますが、実際のところ大学入試に例えるとどのレベルに該当するのでしょうか?偏差値や出題範囲、必要な学習時間などから読み解くことで、その難しさをより具体的にイメージすることができます。
この記事では、電験三種の難易度を大学レベルと照らし合わせて解説するとともに、国立大学との比較や、どの大学なら現役合格を狙えるのか、さらには大学生にとって取得するメリットについても詳しくご紹介します。
難易度ランキングで見る位置づけ
電験三種の試験は、国家資格の中でも上位に位置付けられる難関資格として知られています。
資格の難易度を大学入試の偏差値に置き換えて見てみると、いわゆるMARCH(明治・青山・立教・中央・法政)と同等レベル、偏差値にして60から64程度と評価されることが多いです。
これは大学入試に換算しての目安であり、あくまで参考情報ですが、それでもこの数値から試験の難しさをイメージすることができます。
このランキングの中で、例えば司法試験や医師国家試験は東大・京大レベルに相当するとされ、電験三種はその下に位置しながらも、行政書士や宅地建物取引士と並んで“中堅から上位の難関資格”に分類されます。
特に、理系の中でも電気系の専門知識が求められるため、文系出身の受験者にとってはさらに高いハードルとなることもあります。
電験三種は「電力」「機械」「理論」「法規」の4科目すべてに合格しなければならず、それぞれの内容が専門的である点も難易度の高さに影響しています。
また、試験時間が長く、1科目ごとに範囲が広いため、短期間での対策が難しいという特徴もあります。
これらの点から、電験三種は多くの国家資格の中でも「本格的に勉強しなければ合格できない資格」と言えるでしょう。
簡単に取得できるものではないため、しっかりと準備を重ねることが合格への近道です。
合格率が低い理由とは

電験三種の合格率は例年10%前後で推移しており、直近のデータでも13.5%前後という数字が確認されています。
これは他の多くの国家資格と比較しても、かなり低い部類に入ります。
なぜここまで合格率が低くなるのかというと、いくつかの明確な要因が存在します。
まず、出題される4つの科目の範囲が非常に広く、それぞれに異なる専門性が求められることが挙げられます。
「理論」では電磁気や回路など物理の理解が必要で、「機械」では電気機器に加えて情報や制御工学の知識も求められます。
「電力」や「法規」に至っては、覚えるべき用語や法令、計算手順が非常に多く、効率的な暗記と演習が欠かせません。
さらに、受験資格が不要で誰でも受験できるため、記念受験や十分な準備ができていない状態での受験者も多い傾向があります。
これが全体の合格率を下げる要因になっているのです。
仮に勉強時間をしっかり確保し、戦略的に学習を進めている人に絞って合格率を出した場合、実質的にはもう少し高い割合になる可能性があります。
また、マークシート形式でありながら、単純な知識問題だけではなく、応用的な計算問題が多く出題されるため、過去問をやみくもに解くだけでは対応しきれないというのも特徴です。
公式や理論の理解が曖昧だと、選択肢を絞り込むことさえ難しくなります。
このように、電験三種の合格率が低いのは、単に試験が難しいからというだけでなく、試験の特性や受験者層の広さ、そして学習のハードルの高さが複合的に影響している結果といえるでしょう。
難易度が下がったと言われる理由
近年、電験三種の難易度が以前より下がったと感じる受験者が増えています。
この背景には、2022年度からの試験制度の変更が大きく関係しています。
従来、年1回のみだった実施が年2回へと増えたほか、2023年度からはCBT方式(Computer Based Testing)も導入され、受験者の都合に合わせて日程や会場を選べるようになりました。
これにより、受験者はより自分に合ったタイミングで試験に臨むことが可能になり、体調やスケジュールによる不利が減ったとされています。
また、CBT導入によって試験の運営が効率化されたことで、出題傾向にやや変化が見られ、過去に比べて問題の難易度が平均化されたことも指摘されています。
さらに、試験の頻度が増えたことで、短期間に複数回チャレンジできるようになった点も大きなメリットです。
これにより、「1年に1回のチャンスを逃したらまた1年待たなければいけない」といった精神的プレッシャーが軽減され、試験対策を計画的に進めやすくなった受験者が増えました。
ただし、ここで注意したいのは、「試験が易しくなった=合格が簡単になった」という意味ではないということです。
出題内容そのものが大幅に易化したわけではなく、あくまで環境面の改善や受験機会の増加によって、対策が立てやすくなったというのが実情です。
一方で、合格率が20%近くまで上昇した年度もあるため、今後の試験ではバランス調整のために再び難易度が上がる可能性も考えられます。
このような制度の変化は、常に受験生にとって有利に働くとは限らないため、油断せず着実に準備を進めることが重要です。
国立大学とのレベル感を比較

電験三種の難易度を国立大学と比較する場合、まず試験の性質と求められる学力の方向性の違いを理解することが大切です。
大学入試では一般的に幅広い教科を総合的に問われますが、電験三種は電気や物理に関する専門的な知識と計算力が重視されます。
そのため、単純な偏差値だけで比較することはできません。
それでも参考として挙げられるのは、電験三種の難易度が偏差値60~64程度とされている点です。
この数字は、旧帝大レベルには届かないものの、地方の中堅国立大学の合格ラインに近い水準と見なされています。
たとえば、電気電子系の学科を持つ地方国立大学(例:長岡技術科学大学、群馬大学、山口大学など)の入試難易度と、電験三種の勉強量・必要な思考力を比較すると、大きな差はないと感じる人も多いです。
また、試験範囲に関しては、高校物理に加えて専門的な知識が問われるため、大学受験の物理・数学の学習経験が大きな武器になります。
ただし、大学入試と違って一発勝負ではなく、電験三種は科目合格制度を利用することができるため、対策方法にも幅があります。
このように考えると、国立大学の工学部に合格できる学力があれば、電験三種の合格も現実的に狙えると言えるでしょう。
ただし、国立大学の入試では求められない電気法規や実務的な知識が必要な点には注意が必要です。
現役合格できる大学の目安は?
電験三種に「現役合格できる大学」の目安を考えると、MARCHレベル以上の大学に在籍している学生であれば、しっかりと対策をすれば現役での合格も可能です。
偏差値でいえば60前後の学力がある大学が一つの基準とされます。
この判断は、単に学力の高さだけではなく、継続して自学自習に取り組める力があるかどうかが大きく関係しています。
実際、偏差値が高い大学に在籍していても、電験三種の専門性に対応する勉強をしていなければ合格は難しいでしょう。
逆に、偏差値50台の大学であっても、物理や数学の基礎力がしっかりしており、計画的に勉強時間を確保できる学生であれば十分に合格の可能性はあります。
現役合格を目指すうえで重要なのは、どれだけ早く試験対策を始められるかです。
電験三種の勉強時間の目安は約1,000時間とされています。
仮に1日2時間の学習時間を確保するとしても、約1年半は必要になります。
この時間を無理なく確保できるのは、学業やアルバイトとバランスが取れている大学生だからこそ可能とも言えます。
したがって、現役合格を狙うなら、偏差値の高低にとらわれず、自分に合った学習スタイルとスケジュールを確立することが最大のポイントです。
電験三種は大学生にもおすすめ

電験三種は、大学生にとって非常におすすめの国家資格です。
理由は大きく分けて3つあり、「就職活動でのアピールになる」「将来的な収入アップに直結しやすい」「実務経験が不要で今すぐ受験可能」という点が挙げられます。
まず、就職活動においては、電験三種を取得していることで高い評価を得やすくなります。
特に電気・機械・インフラ関連の業界では即戦力として見なされることも少なくありません。
難関資格を在学中に取得したという事実自体が、計画性・努力・専門性の証明になるため、文系・理系問わず企業からの関心を集める武器になります。
次に、電験三種は資格手当や待遇に直結しやすい点が魅力です。
免状取得後は、設備管理や工場の保守部門などで法的に配置が必要な人材として重宝されるため、年収アップにもつながります。
実際に、電験三種の保有者は年収400万~600万円台が目安となっており、キャリアを積めばさらに高収入を目指せます。
さらに、電験三種には年齢や学歴などの受験資格がないため、大学1年生でも申し込めばすぐにチャレンジできます。
この点で、他の難関資格よりも取り組みやすく、在学中に取得しておくことで他の学生と差別化を図れる絶好のチャンスになるのです。
大学生のうちにコツコツと勉強を始めることで、無理なく資格取得を目指せるだけでなく、将来の選択肢も広がります。
特に、理系で就職活動に不安がある人、あるいは文系でも技術系の知識をアピールしたい人にとって、電験三種は非常に価値ある資格と言えるでしょう。
電験三種の難易度を大学でいうと就職にも有利?
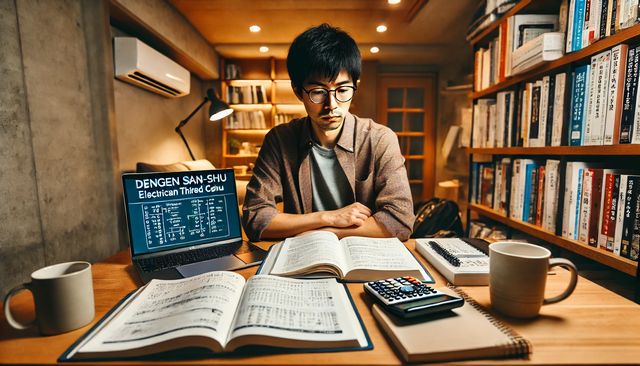
電験三種は難関資格として知られていますが、その価値は「合格の難しさ」だけではありません。
特に注目すべきなのが、就職や転職における評価の高さです。
資格を活かせる職場は非常に多く、電力・インフラ業界はもちろん、製造業や建設業界などでも電験三種の保有者は重宝されます。
ここでは、電験三種を取得することで目指せる年収の水準や、広がる将来の選択肢、さらに今後の需要やキャリアアップの可能性について詳しくご紹介していきます。
学生バイトとの両立は可能か?
電験三種の試験勉強は、学業に加えてアルバイトをしている学生にとっても十分に両立が可能です。
ただし、無理なく進めるには、時間の使い方に工夫が必要になります。
特に重要なのは、日々の生活の中に学習の「習慣」を組み込むことです。
例えば、アルバイトがある日は移動中に参考書を読む、動画講座を活用してスキマ時間に知識をインプットするなど、短時間でも集中して学習する姿勢が求められます。
実際に、1日2時間の学習を続ければ1年間で約700時間以上の勉強時間を確保できます。
これは電験三種に必要とされる学習時間(目安:1,000時間)に近づく十分なボリュームです。
ただし、試験直前期にはバイトのシフトを減らすなどの調整も必要です。
仕事の疲労が学習効率を下げる可能性もあるため、無理をせずに生活のバランスを取ることが重要となります。
このように、電験三種は難易度の高い資格ではありますが、スケジュール管理を意識すれば学生バイトとの両立は可能です。
目標を明確にし、計画的に勉強時間を確保できれば、学業・バイト・資格取得の3つを同時に成立させることも夢ではありません。
難易度比較:他資格とどう違う?

電験三種は、他の国家資格と比較しても難易度の高い部類に入ります。
特に比較対象になりやすいのが、電気工事士、宅地建物取引士(宅建)、行政書士などです。
これらの資格と比べると、電験三種は出題範囲が非常に広く、数学的な知識や理論の理解を必要とする点で大きな違いがあります。
例えば、第二種電気工事士の合格率が60から70%であるのに対し、電験三種は10から20%前後と低水準です。
単に知識を暗記するだけでなく、公式を使った応用計算や複数の概念を組み合わせて答えを導く問題が多いため、文系出身者や数学に苦手意識のある人にはハードルが高いと感じられることもあります。
また、他資格では試験範囲が1冊のテキストで収まることが多いのに対し、電験三種は4科目にまたがり、それぞれに対策が必要です。
そのため、学習時間も多く見積もらなければなりません。
このような特性から、単純な合格率だけではなく、「どのような力を求められるのか」という視点で難易度を判断することが大切です。
電験三種は理論的な思考力や継続的な学習力を求められる資格であり、合格すればそれだけ価値のある専門性が身に付きます。
「役に立たない」は誤解?実はすごい理由
「電験三種は役に立たない」という意見を見かけることがありますが、それは事実と異なる印象です。
むしろ、電験三種はキャリアにおいて非常に実用的かつ市場価値の高い資格の一つです。
この資格が「すごい」と言われる理由は、法律で定められた独占業務があることにあります。
たとえば、一定規模以上の電気設備を扱う施設では、電気主任技術者の設置が義務づけられています。
これは病院や商業施設、工場など、社会インフラを支える現場で必要とされる専門職であり、電験三種の取得者はこれらの現場で直接的に活躍できるのです。
資格を保有していなければ担えない業務が存在することが、電験三種の大きな強みです。
さらに、電験三種は実務経験がなくても受験可能であり、若いうちに取得することで将来の選択肢が広がります。
就職・転職市場では「即戦力」として見なされやすく、技術職やインフラ系企業での需要は年々高まっています。
また、再生可能エネルギーやデータセンターの増加に伴い、電力設備の維持管理が今後さらに重要視される中で、電験三種の価値はますます高まると考えられます。
単に「持っているだけ」では意味がないというのはどの資格にも共通しますが、正しく活用すれば、電験三種はまさに“将来に強い”国家資格なのです。
目指せる年収の目安

電験三種を取得することで、年収はおおよそ400万円から550万円程度を目指すことが可能です。
もちろんこれはあくまでも平均的な水準であり、実際の年収は就職先の業種や職種、地域によっても大きく異なります。
例えば、民間企業のビル管理や設備保守などでは年収400万円前後が一般的ですが、発電所や変電所など公共インフラの電気設備に携わる場合は、年収600万円以上を得ているケースもあります。
また、電験三種の保有者は資格手当を別途支給されることが多く、それが月数万円にのぼることもあります。
さらに、実務経験を積んで電験二種や一種へとステップアップすることで、年収は700万円以上も視野に入ってきます。
特に、電気主任技術者として企業のエネルギー管理を任されるポジションに就けば、役職手当や責任手当が加算され、待遇が一気に上がることもあります。
このように、電験三種は取得するだけでも一定の収入を確保できる資格であり、キャリアを積み重ねれば年収アップにも直結する力強い武器となります。
広がる将来の選択肢
電験三種を取得することで、将来の進路や働き方に幅広い選択肢が生まれます。
この資格は「電気設備の保安監督」という法的に独占された業務に対応しているため、設備管理やインフラ系の現場で重宝されるだけでなく、自らのキャリアを自由に設計しやすくなります。
例えば、企業の設備管理部門に勤務するほかにも、ビルメンテナンス会社や工場の保全部門など、多くの業種で活躍するチャンスがあります。
さらに、再生可能エネルギーの拡大や省エネニーズの高まりを背景に、再エネ関連企業やエネルギーコンサルティング業務への転職にも有利です。
また、独立という選択肢も視野に入ります。
一定の実務経験を積んだ後、個人事業主としてフリーの電気技術者になることも可能です。
このような働き方を選べば、勤務場所や報酬面でも自分の裁量で調整できるようになります。
さらに、電験三種は他の資格と組み合わせることで、より高度な業務にも対応できます。
たとえば電気工事士や施工管理技士などとのダブルライセンスによって、設計から施工、保守までの一連の業務をこなせるようになり、企業からの信頼も高まります。
このように、電験三種の取得は就職・転職のチャンスを広げるだけでなく、将来的な独立やスキルアップの可能性を広げる「選択肢を持てる資格」だといえるでしょう。
需要とキャリアアップの可能性

電験三種の需要は、今後も安定して高い水準が続くと予測されています。
その背景には、電力インフラの老朽化対策や再生可能エネルギーの拡大といった社会的な動きがあるためです。
とくに、AIやIoTの進化に伴い、データセンターなどの大規模な電力設備が急増しており、電気主任技術者の重要性はますます高まっています。
こうした流れの中で、電験三種の保有者は企業にとって欠かせない人材として位置づけられることが多く、将来にわたって需要が途絶えることは考えにくい状況です。
さらに、電気の管理業務は法令に基づいて「有資格者でなければ行えない」と定められているため、資格の価値が下がることもありません。
また、キャリアアップを目指す場合にも電験三種は優れたスタート地点となります。
例えば、実務経験を積むことで電験二種・一種への挑戦が可能になりますし、マネジメント系の資格やエネルギー管理士などと組み合わせてキャリアの幅を広げることもできます。
一方で、こうしたキャリアアップには継続的な学習と努力が欠かせません。
取得後も現場での経験を積みながら、電気法規や技術の変化に柔軟に対応する姿勢が求められます。
電験三種は、取得した時点での価値も高いですが、継続的なキャリア形成においても長期的に役立つ資格です。
今後の電力業界や社会インフラの動向を見ても、その重要性はむしろ増していくでしょう。
【まとめ】電験三種の難易度を大学でいうとを総括
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。