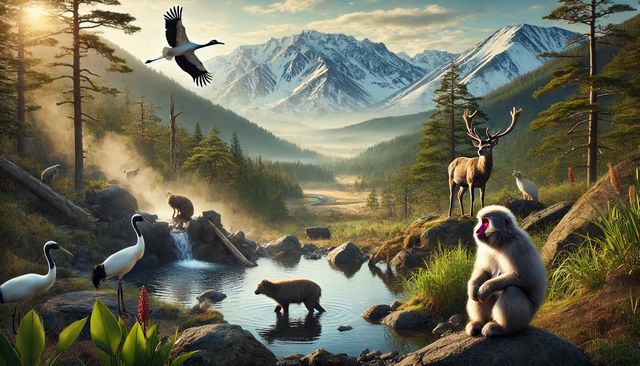狩猟を始めたいと考えたとき、最初に気になるのが狩猟免許の難易度ではないでしょうか。ネット上の知恵袋などを見ると「意外と簡単」といった声もある一方で、「実技で減点されて落ちた」「筆記試験が難しかった」といった体験談も多く見られます。特に第一種・第二種や銃の扱いを伴う免許では、求められる知識や動作のレベルが高くなるため、不安を感じる方も多いはずです。
また、「罠だけの免許なら簡単なのか」「誰でも取れるものなのか」といった疑問を持つ方もいるでしょう。さらに、受験にかかる費用や補助金の有無、合格したら何をすべきか、取り方の流れまで気になるポイントはたくさんあります。
この記事では、狩猟免許の種類ごとの違いや試験内容、筆記・実技の注意点、地域によって特色のある北海道での受験事情までを詳しく解説します。難易度を下げるためのおすすめ問題集や勉強法も紹介しますので、これから狩猟を目指す方はぜひ参考にしてください。
■本記事のポイント
- 狩猟免許の筆記試験と実技試験の内容と対策方法
- 第一種・第二種や罠だけの免許の違いと難易度の差
- 合格後に必要な手続きやかかる費用の詳細
- よくある失敗例と合格率を上げるためのポイント
狩猟免許の難易度は高い?試験内容と対策

狩猟免許の取得を目指す多くの方がまず気になるのは、「試験ってやっぱり難しいの?」という点ではないでしょうか。
狩猟と聞くと専門的でハードルが高いイメージを持たれがちですが、実際の試験内容はしっかりと対策すれば十分に対応可能な範囲に収まっています。
ここでは筆記試験・実技試験の具体的な内容や、減点を防ぐための重要ポイントを順に解説していきます。
特に初受験の方でも分かりやすいように、必要な準備や気をつけたい落とし穴を丁寧に紹介していきますので、ぜひ読み進めてください。
筆記試験は難しい?
狩猟免許の筆記試験は、正しく対策をすれば決して難しくはありません。
ただし、出題内容に独特のクセがあるため、事前の準備が重要になります。
問題数は1種類の免許を受ける場合で30問、試験時間は約90分間です。試験は三択形式ですが、単純な暗記だけでは対応しきれない問題も含まれています。
というのも、近年の狩猟免許試験では、問題文が長文化する傾向が強くなっており、3から7行にわたる文章の中に複数の論点が含まれていることが多いからです。
例えば「鳥獣保護管理法に基づいた有害鳥獣の駆除とは何か」といった内容を中心に、関係法令や狩猟の制度、個体数の管理に関する知識などが混在した問題が出題される場合があります。
こうした出題傾向に対応するには、単に選択肢を覚えるだけでなく、問題集や参考書の解説文をしっかり読み込み、背景となる制度や概念を理解しておくことが必要です。
特に法律や鳥獣に関する用語に不慣れな方は、最初の数時間は用語の定着に時間がかかるかもしれませんが、一度基礎が身につけば、同じような形式の問題が繰り返し出るため得点を積み上げやすくなります。
このように、筆記試験は工夫しながら勉強すれば十分に合格できるレベルです。
実際、初心者講習会を受けたうえで10から20時間程度の学習時間を確保すれば、70%以上の正答率は難しくないと言われています。
重要なのは、問題のパターンに慣れることと、引っかけ問題に惑わされない読解力を身につけることです。
実技の減点方式のポイントとは

狩猟免許の実技試験は、受験者がもっとも苦戦しやすいパートの一つです。
というのも、この試験は減点方式で採点され、減点が累計で30点以上になると即不合格になるためです。つまり、「いかに失点を抑えるか」が合格の鍵となります。
実技試験は主に「鳥獣判別」「距離の目測」「猟具の取り扱い」の3つのセクションに分かれており、試験内容は免許の種類によって若干異なります。
たとえば、第一種銃猟ではすべてのセクションを行いますが、網猟・わな猟では距離の目測が省略されます。
この減点方式の試験で特に注意したいのが、「初歩的なミスによる大幅減点」です。
たとえば、鳥獣判別では非狩猟鳥獣を誤って狩猟対象と答えると2点減点、目測では誤差があれば1問で5点の減点になります。
猟具の取り扱いでは、銃口の向きや操作ミスにより一気に10点以上減点されることもあるため、細かな動作にも神経を使う必要があります。
また、実技試験では緊張感のある雰囲気の中で行動を求められるため、普段ならしないようなミスをしてしまうことも少なくありません。
これを防ぐには、予備講習で模擬銃を扱いながら体に覚え込ませておくことが効果的です。
特に「銃を持ったまま向きを変えるとき」や「分解・結合中の銃口の向き」など、うっかりミスしやすいポイントを意識的に反復練習しておくと安心です。
実技試験では完璧さよりも「減点を最小限にとどめる」意識が大切です。
合格ラインは70%以上の得点、すなわち100点中30点以上の減点で不合格となるため、合格には正確性と慎重さが求められます。
銃の取り扱いで注意すべき減点要素
銃猟免許を取得するための実技試験では、銃の取り扱いに関する正しい知識と動作が求められます。
このセクションでは、誤った操作が減点につながるリスクが最も高いため、注意点をしっかり把握しておく必要があります。
まず絶対に避けなければならないのが、「銃口を人に向けてしまうこと」です。
試験官や他の受験者に銃口が向いた場合、それだけで大幅な減点となるだけでなく、試験の継続が認められない可能性もあります。
このため、銃を取り扱う際は常に銃口の向きを意識し、「銃口からレーザーが出ている」と想定しながら動作すると安全です。
次に注意したいのが、「引き金(トリガー)への不適切な接触」です。
指示があるまで引き金に指をかける行為は重大な減点対象になります。
これは安全管理の観点から非常に重要視されており、特に初めて銃を扱う方は、無意識に指が引き金に触れてしまうケースがあるため注意が必要です。
グリップを握る際は、すべての指を引き金から外し、ピタッとそろえておくことが基本です。
さらに、銃の分解・結合の際にも注意点があります。この工程では「声出し」が求められることが多く、たとえば「点検完了しました」「異物なし」「分解完了しました」など、要所要所での報告が欠けると減点対象となることがあります。
こうした声出しのルールは、初心者講習会や予備講習で繰り返し教わるため、体に染み込ませておくと良いでしょう。
また、休憩時の銃の置き方や団体行動時の銃の保持方法にも評価基準があります。
銃をテーブルに置くときに銃口が動いてしまうと減点されるため、落ち着いてゆっくりとした動作を心がけることが大切です。
これらの要素はどれも一つ一つはシンプルな内容ですが、試験本番で緊張していたり、流れが分からなかったりすると、簡単に減点につながります。
確実に合格するためには、実技の一連の動作を自信を持ってこなせるよう、事前に模擬訓練を重ねることが有効です。
罠だけ取得したい場合の難易度

罠猟免許だけを取得したいと考えている方にとって、その難易度は比較的低いといえます。
これは、銃猟免許と比較して試験内容がシンプルで、身体的な条件も緩やかであるためです。
罠猟は猟銃を使用しないため、銃の分解・組立や射撃姿勢の確認といった実技の要素がありません。
したがって、技能試験の中でも「猟具の取り扱い」と「鳥獣の判別」が中心となります。
罠猟免許で必要な技術として求められるのは、捕獲可能な状態に罠を正しく組み立てることと、禁止猟具との区別を正確にできるかどうかです。
この点においては、しっかりと教材を使って基本的な種類や組み立て方法を理解していれば、大きく減点されることは少ないでしょう。
事前に予備講習などで実際の罠に触れておくと、より理解が深まります。
また、目測の試験が無い点も罠猟免許の特徴です。
第一種・第二種銃猟免許には距離感覚を問う目測試験が課されますが、罠猟の場合はそれが免除されており、プレッシャーも少なくなります。
知識試験に関しても、罠猟の範囲は銃猟に比べて限定的です。
とはいえ、鳥獣保護法や関連する法令、捕獲対象の生態などは問われるため、油断は禁物です。
特に、狩猟鳥獣と非狩猟鳥獣の判別では細かい知識が求められるため、十分に練習を積むことが必要です。
このように、罠猟免許は「初めて狩猟に関心を持った方」にとっても入りやすい免許といえるでしょう。
ただし、簡単に取れると油断すると失敗につながります。あくまでしっかりと準備した上で受験に臨むことが重要です。
取り方と必要な準備
狩猟免許を取得するには、まず居住地の都道府県で実施される試験を受ける必要があります。
試験は毎年数回実施されており、事前に申請書を提出することから始まります。
免許の種類によって年齢制限があり、罠・網猟は18歳以上、銃猟免許は20歳以上が対象です。
申請に必要な書類は複数あります。
主なものとしては、狩猟免許申請書、医師の診断書(精神疾患や薬物依存でないことの証明)、証明写真、そして申請手数料の支払いです。
これらは都道府県ごとに様式が異なる場合もあるため、事前に公式サイトや役所で確認しておくとスムーズです。
試験に向けた準備としては、任意で実施されている「狩猟免許予備講習会」への参加が強く推奨されます。
この講習では知識試験・技能試験に必要な内容を実際に体験しながら学べるため、初受験者には非常に心強い内容です。
特に銃猟免許を希望する場合は、模擬銃の分解・操作などを事前に練習しておくことが、合格の鍵になります。
さらに、知識試験に対応するための問題集や参考書も必要です。
法令や狩猟制度に関する知識は、日常的に触れる機会が少ないため、繰り返し学習することが不可欠です。
基礎が理解できれば、過去問と似た形式の問題が多いため、得点につながりやすくなります。
試験当日は、受付・説明・筆記試験・適性試験・昼食・実技試験という流れで進行します。1日がかりの長丁場となるため、体調を整えて集中力を保つ準備も大切です。
飲み物や軽食、筆記用具、マーカーペンなどの持参も忘れないようにしましょう。
狩猟免許の取得は一見難しそうに感じられますが、必要な準備を段階的に進めれば、しっかりと合格を目指すことができます。
おすすめ問題集とは

狩猟免許の筆記試験対策として、市販の問題集を活用することは非常に効果的です。
特に初心者にとっては、専門的な用語や法制度に慣れるための入口として、わかりやすく整理された問題集を使うことが合格への近道となります。
市販されている問題集の中には、「法令」「猟具の知識」「鳥獣の生態」などの項目が章ごとに分かれており、試験に出題される範囲を体系的に学べる構成になっているものがあります。
解説が丁寧で、初心者でもつまずきにくい内容になっている問題集を選ぶのがポイントです。
例えば、「猟銃等講習会考査 絶対合格テキスト&模擬試験5回分」は、基礎から応用まで網羅しており、実際の試験に近い形式で演習ができると評判です。
また、「猟銃等講習会試験対策例題集Ⅲ」も、引っかけ問題や長文問題への対処法を練習するのに適しています。
これらはAmazonや楽天などで購入可能で、2冊あわせても4,000円前後と手頃な価格帯です。
問題集を選ぶ際には、「最新版であるか」も確認しておきましょう。
狩猟関連の法令や制度は改正が行われることもあるため、古い情報では正しい対策ができない可能性があります。
さらに、書籍だけでなく、スマートフォンで学習できるアプリやWeb教材も活用すれば、通勤時間やスキマ時間を使って学習を進めることができます。
繰り返し問題に触れ、間違えたポイントを確認することが、合格への最短ルートです。
このように、適切な問題集を選び、計画的に学習を進めることで、筆記試験への不安を大幅に軽減することができます。
特に初受験の方は、最初から複数の問題集に取り組むより、1冊を徹底的にやり込む方が効果的です。
狩猟免許の難易度の実態と合格率

狩猟免許の試験は、合格率が高いと言われる一方で、実際には毎年一定数の不合格者が出ており、「本当に誰でも受かるのか?」と不安に感じる方も少なくありません。
ここでは、第一種と第二種の違いをはじめ、実際の合格率や落ちた人の共通点、合格後に必要な手続きなどを詳しく解説していきます。
また、北海道のように地域によって試験の事情が異なるケースもあるため、全国共通のポイントだけでなく、地域特有の傾向も押さえておきましょう。
第一種・第二種の違いと難易度比較
狩猟免許には「第一種銃猟免許」と「第二種銃猟免許」があります。
どちらも銃を使用する免許ですが、その扱える銃の種類と試験内容に違いがあります。
これらの違いを理解しておくことで、自分に合った免許の選択や試験対策がしやすくなります。
第一種銃猟免許では、散弾銃・ライフル銃・空気銃などを使用した狩猟が可能です。広範な猟法に対応できるため、より実践的で本格的な狩猟を目指す人に向いています。
一方、第二種銃猟免許は空気銃(エアライフル)のみを使用することができ、主に小型の鳥類を対象とした狩猟が中心です。
試験の難易度で比較すると、第一種のほうが高めです。これは、扱う銃の種類が多く、技能試験に含まれる操作の項目数も多いためです。
たとえば、第一種では「上下2連銃」「自動銃」など複数種類の模擬銃を扱う必要があり、分解・結合・脱包・団体行動など、求められる動作の数が増えます。
また、目測試験では300mや50mなど複数の距離の判別も求められ、ここでも難易度が上がります。
第二種はこれらの操作が省略または簡略化されているため、技能試験の範囲が狭く、初心者でも挑戦しやすいと言えるでしょう。
ただし、空気銃特有の圧縮操作なども正確に行う必要があるため、まったくの準備不足では通用しません。
このように、第一種と第二種の難易度には差がありますが、それぞれの目的に応じて選択することが大切です。
幅広い猟法を行いたい人は第一種を、より手軽に狩猟を始めたい人は第二種を選ぶと良いでしょう。
合格率と「落ちた」理由

狩猟免許試験の合格率は、一般的に80%前後といわれていますが、必ずしも「簡単に合格できる試験」というわけではありません。
実際には、筆記・適性・技能の3つの試験すべてに合格しなければならず、どこかで失点が重なると不合格になるケースが少なくないのです。
多くの受験者が「落ちた」と感じる最大の理由は、技能試験での減点による失格です。
技能試験は減点方式で、30点以上の減点があると不合格になります。
特に銃口の向きや引き金への接触といった基本的なルール違反による失点は目立ちます。
こうした減点は一度に10点以上になることもあり、数回のミスで不合格ラインに達してしまうことがあります。
また、鳥獣判別の試験でも油断は禁物です。見慣れない鳥獣の写真を瞬時に判断しなければならず、「非狩猟鳥獣」に誤って狩猟種名を記入してしまうなど、焦りからのミスが続くと大きな減点になります。
さらに、距離の目測試験では誤差の判断が難しく、特に30mと50mの見極めが苦手という受験者が多く見られます。
筆記試験では、問題の文章が長く引っかけも多いため、読解力や冷静な判断力が求められます。
直前の詰め込みだけでは対処できない部分があるため、十分な準備をしていないと対応しきれない可能性もあります。
このような背景を踏まえると、合格率が高いように見えても、しっかりとした対策なしには通過できない試験であることがわかります。
「落ちた」原因の多くは、準備不足と基本動作のミスです。講習会の受講や、繰り返しの練習が非常に重要です。
合格したらどうすればいいのか
狩猟免許試験に合格しても、すぐに狩猟ができるわけではありません。
試験に合格した後には、さらにいくつかの手続きを経て正式に狩猟が可能になります。具体的には、「狩猟者登録」と「銃の所持許可の取得」が必要です。
まず、合格後に行うべきなのが「狩猟者登録」です。
これは、狩猟を行う都道府県で登録を行い、「狩猟者登録証」と「狩猟者バッジ」を受け取ることで完了します。
狩猟を行うにはこのバッジの携帯が義務づけられており、登録をしていない状態で狩猟行為を行うと処罰の対象となります。
このとき、狩猟税と登録手数料の支払いも必要になります。
免許の種類によって金額が異なり、例えば第一種銃猟では18,300円、わな猟では10,000円が必要です。支払い方法は収入印紙で行われるのが一般的です。
次に、銃を使用した狩猟を行う場合は「銃の所持許可」が必須です。
これは狩猟免許とは別に警察の管轄で行われるもので、筆記試験・面接・実技講習・身辺調査などをクリアしなければ許可が下りません。
許可取得には数ヶ月かかることもあるため、狩猟シーズンに間に合わせるためには、早めの準備が欠かせません。
さらに、火薬を使用する場合は「火薬類譲受許可」も必要になることがあります。
これも公安委員会への申請が必要で、書類の提出と審査を経て許可証が交付されます。
このように、狩猟免許に合格した後にも多くの手続きが待っています。
どの段階でもしっかりと情報収集を行い、段取りよく準備を進めることで、スムーズに狩猟を始めることができるでしょう。
北海道での狩猟免許の実情

北海道は日本の中でも特に狩猟文化が根付いており、広大な自然環境を活かした狩猟が盛んに行われています。
そのため、狩猟免許の取得を目指す人も多く、道内では年に複数回の試験が実施されています。
北海道で狩猟免許を取得する場合、基本的な試験内容は他の都道府県と大きく変わりません。
筆記試験・適性試験・技能試験という構成で、受験資格や合格基準も全国共通です。
ただし、地域によっては鳥獣の種類や分布に違いがあるため、出題される鳥獣判別の問題に地域特有の傾向が見られることもあります。
また、北海道ではクマやエゾシカといった大型獣が対象となることも多く、特に第一種銃猟免許の需要が高い傾向にあります。
実際、狩猟対象の動物が多い地域では、それに応じた銃の扱いが求められるため、試験対策の段階から本格的な知識と技能が求められるケースもあります。
一方で、広い面積に対して試験会場が限られているため、移動に時間がかかるという課題もあります。
試験の開始時間が早朝に設定されていることも多く、遠方からの受験者は前日からの移動や宿泊を視野に入れる必要があるでしょう。
実際、試験当日に疲労や寝不足から本来の実力を発揮できないというケースもあるようです。
北海道で狩猟を行うには、積雪や気象条件も考慮しなければなりません。
これに対応するため、免許取得後も雪道での移動や寒冷地での活動に慣れることが重要です。
このように、北海道での狩猟免許取得は環境的な特性や対象鳥獣の違いなど、独自の要素を多く含んでいます。
地域に応じた対策を取ることで、より実践的で安全な狩猟活動に繋げることができるでしょう。
狩猟免許の費用と補助金の有無
狩猟免許を取得するには、試験の受験料だけでなく、講習会費用や診断書の発行など、さまざまな費用が発生します。
これらを合計すると、想定よりも費用がかかると感じる方もいるかもしれません。ここでは具体的な内訳と、補助金の有無についてわかりやすく説明します。
まず、狩猟免許試験の受験手数料は1種類あたり5,200円です。
複数の免許を同時に受ける場合はその分の費用が加算され、2種類であれば10,400円になります。
また、万が一不合格となった場合の再受験料は3,900円です。
次に必要となるのが医師による診断書の発行費用です。
これは精神疾患や薬物依存がないことを証明する書類で、病院によって価格に差はありますが、おおよそ5,000円前後と見ておくとよいでしょう。
さらに、任意ではあるもののほぼ必須とされる「狩猟免許予備講習会」の参加費も見逃せません。
こちらは1万円から1万5,000円程度が相場です。
講習内容は実技や筆記の対策を含み、模擬銃を使った訓練ができるため、技能試験対策として非常に効果的です。
合格後にも「狩猟者登録費用」が必要となります。
たとえば、第一種銃猟の場合は狩猟税と手数料を合わせて18,300円、わな猟では10,000円が必要です。
では、補助金は受けられるのでしょうか?
これは自治体によって異なります。
一部の市町村では、有害鳥獣駆除や地域の猟友会活動への参加を条件に、講習費用や狩猟登録費用の一部が助成される制度があります。
制度の内容や対象は地域によって大きく異なるため、住んでいる自治体や地元の猟友会に確認することをおすすめします。
このように、狩猟免許取得には複数の費用がかかりますが、補助制度を活用すれば負担を軽減できる場合もあります。
無理なく準備を進めるためにも、あらかじめ費用の全体像を把握しておくことが大切です。
難しいですか?誰でも取れる?

「狩猟免許って難しそう…本当に自分に取れるの?」と不安に感じる方は多いようです。
確かに、狩猟というと専門性が高く、命を扱う責任ある行為という印象が強いため、ハードルが高いと思われがちです。しかし、正しく対策すれば誰でも取得を目指せる資格です。
実際、試験の合格率はおおむね80%前後とされており、特別な学歴や体力が求められるわけではありません。
受験資格さえ満たしていれば、年齢や職業を問わず、多くの人がチャレンジしています。
筆記試験についても、問題集を使って繰り返し学習すれば内容を理解できる構成になっており、専門知識ゼロからでも始められます。
ただし、「誰でも取れる=何もせずに取れる」というわけではありません。特に技能試験では、模擬銃を使った分解や取り扱い、鳥獣の識別など、実際の動作を評価されます。
これらは講習会で一度体験しておかないと、本番でスムーズに動けず減点されてしまう可能性があります。
また、視力や聴力、四肢の可動域などをチェックする適性試験もあります。
大きなハンディキャップがなければほとんどの方が合格できますが、眼鏡の持参忘れなどの初歩的なミスにも注意が必要です。
このように、しっかり準備をすれば「難しい」と思っていた狩猟免許も現実的な目標になります。
情報収集をしっかり行い、段階を追って対策すれば、誰でも無理なく合格を目指せる資格です。
知恵袋ではどう語られている?
「狩猟免許 難易度」についてネットで検索すると、多くの人がYahoo!知恵袋などのQ&Aサイトで実際の体験談やアドバイスを共有しています。
これらの情報は、受験を考えている人にとって非常にリアルで参考になりますが、一方で注意すべき点もあります。
まず、知恵袋には「意外と簡単だった」「講習をちゃんと聞いてれば合格できる」といった声が見られます。
特に筆記試験については、「初心者講習で聞いた内容ばかりだった」「問題集の内容と似たようなものばかりだった」という意見も多く、事前の勉強で十分対応できるという印象を与えています。
一方で、「技能試験で落ちた」「想像以上に緊張した」といった書き込みも少なくありません。
特に実技に関しては、受験者が当日緊張して銃口の向きを誤ったり、引き金に触れてしまったりして大きく減点される事例が報告されています。
また、「講習の時間が長くて眠気との戦いだった」「当日の復習時間がほとんどなかった」というような、当日の流れに関する具体的な注意点も多く共有されています。
このように、知恵袋では肯定的な意見と否定的な意見の両方が見られます。
人によって感じ方や受験の状況は違うため、情報をそのまま鵜呑みにせず、複数の書き込みを比較しながら参考にするのが賢明です。
また、知恵袋の情報は内容が古かったり、地域差がある場合もあるため、最終的には公式情報や講習会での指導内容を優先して判断しましょう。
知恵袋はあくまで「現場の声」として捉え、受験対策の参考材料の一つとして活用するのが効果的です。
【まとめ】狩猟免許の難易度を総括
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。
罠猟免許は範囲が限定的で比較的取得しやすい