大学院の入試を目指すにあたって、大学院入試の難易度は誰もが気になるテーマです。
特に、国立 大学院 難易度や大学院 倍率 一覧といった具体的な情報を探している方にとっては、志望校や専攻を選ぶうえで重要な判断材料となります。
本記事では、大学院の難易度を「倍率」「ランキング」「専攻ごとの傾向」など多角的な視点から解説します。
東大 大学院、京都大学 大学院、大阪大学 大学院などの難関校をはじめ、名古屋大学、東北大学、九州大学、北大、東工大、一橋大学などの大学院といった旧帝大、さらには早稲田大学、中央大学などの大学院といった有力私大の入試傾向についても紹介。
放送大学の大学院のような社会人に人気の大学院や、税理士で大学院入試の難易度ランキングで注目される実務系大学院についても触れていきます。
さらに、大学院に簡単に入れる専攻はあるのか?という疑問にも答えながら、あなたの進学戦略に役立つ情報をお届けします。
■本記事のポイント
- 大学院入試の難易度は専攻や研究室によって異なること
- 倍率やランキングを参考に難易度を比較できること
- 簡単に入れる大学院や専攻の傾向があること
- 有名大学院ごとの入試特徴や対策ポイントがわかること
大学院入試の難易度を徹底解説

大学院入試の難易度は、学部入試のように偏差値で一律に測れるものではありません。
専攻分野や大学ごとの方針、研究室の人気度など、さまざまな要素が絡み合って決まります。
そのため、「難易度が高い」と一言で言っても、その中身はとても複雑です。
ここでは、倍率やランキング、大学別の傾向など、多角的な視点から大学院入試の難易度について詳しく解説していきます。
志望校選びや受験戦略の参考になる情報を順を追ってご紹介します。
国立大学院の難易度の特徴とは
国立大学院の入試難易度には、いくつかの明確な傾向があります。
特に注目すべき点は、「入試難易度が大学の知名度や偏差値とは必ずしも比例しない」という点です。
大学院は研究を行う場であり、学部入試のように一律の学力テストで競い合うわけではありません。
したがって、大学院の難易度は、志望する研究室の人気や、研究分野の専門性、受験方式によって大きく異なります。
一方で、国立大学院は学費が比較的安価で、教育・研究体制が整っていることから、志望者が集中しやすいという特徴もあります。
特に旧帝大(東京大学、京都大学など)や、専門性の高い国立大学(東京工業大学、一橋大学など)の大学院は、研究レベルの高さや就職実績が評価され、毎年高倍率となる傾向があります。
ただし、入試で求められるのは「知識の深さと研究適性」であり、単に暗記力や処理スピードで勝負する大学学部の試験とは性質が異なります。
このため、研究計画書の質や、面接時のプレゼン能力なども合否に大きく影響します。
そのため、国立大学院の難易度は一概に語ることが難しく、志望分野と研究室の状況を事前にしっかり調査しておくことが重要です。
倍率一覧で見る難易度の傾向

大学院の入試難易度を把握する方法のひとつに、「倍率一覧」を見るという方法があります。
倍率とは、志願者数に対する合格者数の割合を示す数値であり、高倍率ほど競争が激しいことを意味します。
ただし、倍率がそのまま難易度を表すわけではないため、読み解き方には注意が必要です。
例えば、ある大学院の倍率が3倍だったとしても、そもそもの志願者の層が限定的で専門性の高い分野であれば、受験者の質も高く、実質的な難易度はさらに上がります。
逆に、倍率が低くても、研究計画書や面接に対する評価が厳格な大学院では、簡単に合格できるとは限りません。
倍率の一覧を見る際には、研究科ごとの志望傾向も考慮しましょう。
理系の大学院では比較的倍率が安定しており、1.0~1.5倍程度が多く見られます。
一方、文系の大学院は定員が少ないこともあり、倍率が3倍を超えるケースもあります。
これに加えて、内部進学か外部進学かによっても合格率は変わってきます。
多くのデータでは、内部進学者の合格率が外部進学者より高いことが示されています。
したがって、倍率を見る際は、単に数値だけでなく、内部・外部、専攻ごとの背景にも注目することが大切です。
簡単に入れる専攻はある?
「大学院に簡単に入れる専攻はあるのか?」という疑問を持つ方も多いかもしれません。
結論から言えば、確かに倍率が低く、比較的合格しやすいとされる専攻も存在します。
ただし、「簡単に入れる」かどうかは、あくまで相対的なものであり、油断は禁物です。
一般的に、理系の一部の分野では志望者が少なく、定員割れを起こすケースもあります。
特に、ニッチな研究テーマや、特殊な技術分野に関する専攻では、受験者が限られるため、合格率が高い傾向があります。
また、地域的に志望者が集まりにくい地方大学の研究科でも、同様の傾向が見られます。
ただし、これらの専攻に合格するためには、当然ながらその分野への適性や研究意欲が求められます。
研究計画書の質が低かったり、面接でのやりとりに一貫性が欠けていたりすると、定員に空きがあっても不合格となる可能性はあります。
そのため、「簡単に入れるから」といった理由だけで専攻を選ぶのではなく、自分の興味やキャリアプランと照らし合わせながら検討することが重要です。
ランキングで難易度比較

大学院の入試難易度を比較する上で、「ランキング形式」の情報は非常に参考になります。
ただし、大学院のランキングは学部の偏差値ランキングとは性質が異なり、「研究成果」や「教育体制」、「就職実績」など多角的な要素で評価される点に注意が必要です。
たとえば、「東大大学院」「京大大学院」などの旧帝大系大学院は、研究環境の充実度や世界的な評価の高さから、常に上位に位置しています。
また、一橋大学や東京工業大学のような専門性の高い大学院も、分野別のランキングでは非常に高い評価を受けています。
このようなランキングを参考にすることで、自分の専攻する分野における大学院の「格」を把握しやすくなります。
ただし、あくまでランキングは目安であり、自分の研究テーマに合った研究室があるかどうか、教員の指導方針がマッチするかといった要素の方が、入試成功の鍵を握ります。
したがって、ランキングに過度に依存せず、希望する大学院の個別情報や研究内容をしっかり確認することが大切です。
税理士の大学院入試の難易度ランキング
税理士資格を目指す上で、大学院進学は一つの有効な選択肢です。
なぜなら、所定の大学院で税法や会計学を修了すると、税理士試験の一部科目が免除されるからです。
こうした背景から、税理士の大学院入試の難易度ランキングは、税理士志望者にとって重要な情報になります。
一般的に、税理士関連の大学院は社会人にも門戸が開かれており、社会人入試や夜間コースを設けている大学院もあります。
その一方で、入試で課される小論文や研究計画書の精度、面接での動機の一貫性など、審査の質は非常に高い水準で求められる傾向にあります。
難易度のランキングでは、中央大学大学院、早稲田大学大学院、神戸大学MBAなどが上位に挙げられます。
これらはいずれも実績・知名度ともに高く、受験者も多いため、倍率が高くなる傾向があります。
一方で、比較的入学しやすいとされる大学院も存在しますが、それでも研究テーマの明確さや、論理的な説明能力がなければ合格は難しいと言えます。
このように、税理士関連の大学院は、「科目免除の恩恵があるからこそ」、しっかりとした準備が求められるという点を忘れてはなりません。
難易度を判断するための情報収集方法
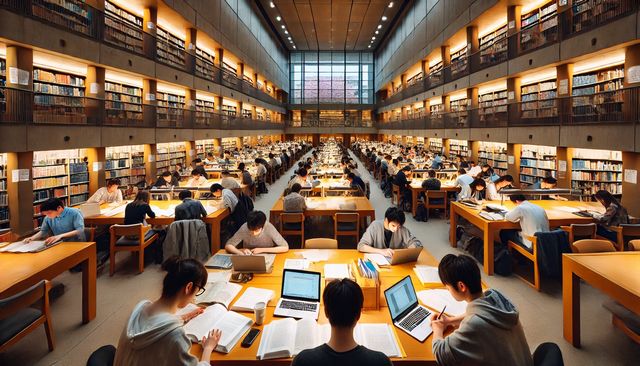
大学院の難易度を正確に把握するには、単に「倍率が高い・低い」といった表面的な情報だけで判断するのでは不十分です。
受験者の実力層、入試方式、研究科の特徴、そして研究室ごとの人気など、複数の要素を組み合わせて判断する必要があります。
まず行うべきは、志望大学院の公式サイトを確認することです。
募集要項や過去問の有無、入試日程、求められるスコア(TOEIC・TOEFLなど)など、基本情報がすべて掲載されています。
次に、合格率や倍率が公表されていれば、それも参考になりますが、数字の裏側にある背景も読み取ることが大切です。
たとえば、倍率が低くても、研究室が少人数制で非常に厳選しているケースもありますし、逆に倍率が高くても合格者が多く、実質的な競争はさほど激しくないこともあります。
さらに、志望先の研究室に直接連絡を取ったり、オープンキャンパスで教員と話をしたりすることで、非公開の情報を得ることができます。
また、現役院生や卒業生のブログやSNSでの情報発信も、リアルな視点として活用できます。
最終的には、複数の情報を照らし合わせ、自分にとって「入りやすいか」「合っているか」を多面的に判断することが、後悔のない選択につながります。
大学院入試の難易度を大学別に比較

大学院入試の難易度は、志望する大学によって大きく異なります。
同じ分野であっても、大学ごとの入試方式や評価基準、研究環境の違いが、合格のしやすさに大きく影響します。
ここでは、国公立・私立を問わず有名大学を中心に、それぞれの大学院の入試事情や難易度の特徴を詳しく見ていきましょう。
志望校選びの参考になる具体的な傾向やポイントを、一つひとつ丁寧に解説していきます。
放送大学大学院の入試事情
放送大学大学院は、社会人をはじめとした多様な学び直し層から高い関心を集めています。
その最大の特徴は、通信制であることに加えて、学習の柔軟性が高く、地理的制約がほとんどない点です。
特に、働きながら修士課程を目指す人にとっては非常に有用な進学先といえるでしょう。
入試に関しては、一般入試と社会人特別選抜があります。
筆記試験がない代わりに、小論文や研究計画書、面接によって選考が行われることが多く、出願書類の完成度が合否に直結します。
特に研究計画書では、自らの研究テーマが放送大学の教育リソースとどのように合致しているかを明確に伝える必要があります。
ただし注意点として、放送大学は通信制であることから、対面での研究指導やゼミ活動の機会は限られます。
そのため、自律的に学習を進める意志と、リモート環境でも研究を継続できる体制が求められます。
学びたいテーマが明確であり、自分のペースで大学院教育を受けたい方には、非常に適した選択肢となるでしょう。
東大大学院の難易度と対策

東京大学の大学院は、国内トップクラスの研究環境を誇り、その分入試の競争も激化しています。
学部入試と異なり、大学院では研究計画の完成度や面接での論理的思考力、専門知識の深さなど、多方面の評価ポイントが存在します。
特に東大では、研究計画書と筆記試験、口述試験の3つを重視する学府が多く、いずれかの準備が甘いと合格は難しくなります。
筆記試験では、学部レベルの専門知識に加え、学際的な問題が出題されることもあるため、応用力も問われます。
また、英語試験にはTOEFLやTOEICのスコア提出が求められる場合もあるため、事前準備が必須です。
加えて、東大の大学院では出願前に指導教員とコンタクトを取ることが半ば常識となっており、事前面談の有無で合否が左右されることすらあります。
この面談では、研究テーマの妥当性や本人の熱意が直接見られるため、準備不足では好印象を与えることは難しいでしょう。
このように、東大大学院の入試には周到な戦略と情報収集が不可欠です。
早期の準備と教員との信頼関係構築が、合格への第一歩となります。
京都大学大学院の入試ポイント
京都大学大学院は、自由な学風と高度な研究水準で知られています。
そのため、受験においても「自発性」や「探究心」が重視される傾向があります。
入試の方式は研究科ごとに異なりますが、一般的には専門科目の筆記試験と面接、そして研究計画書の提出が求められます。
京大の大学院が特徴的なのは、筆記試験の出題内容が幅広く、一般的な知識に加えて論述力や応用力を必要とする点です。
暗記型の試験ではなく、いかに考察力や研究者としての視点を持っているかが問われる問題が多く出題されます。
また、面接試験では提出した研究計画書をもとに、専門教員から鋭い質問が飛んできます。
このとき、研究計画に曖昧な部分があるとすぐに指摘されるため、論理性と一貫性を持った説明が求められます。
加えて、過去問の公開範囲が限られていることが多いため、志望する研究科の傾向を独自に調べる努力も必要です。
このような背景から、京都大学大学院の入試では、単なる受験対策ではなく、本質的な研究者としての資質が求められていることがわかります。
大阪大学大学院は難関か?

大阪大学大学院は、西日本を代表する難関大学院の一つとして知られており、研究・教育の水準が高いことから、全国から多くの受験者が集まります。
したがって、入試の難易度は比較的高い傾向にあります。
特に理系の専攻では、筆記試験に加えて研究室の事前訪問や教員との面談が重要な要素となっており、試験そのものの難しさ以上に、事前準備が合否に影響します。
多くの研究科では、出願前に指導教員との事前面談を推奨しており、研究テーマとの親和性や、指導方針との相性が重視されます。
また、外部受験生にとっては、内部進学希望者との競争になることも少なくありません。
内部生は既に研究室に所属していることが多く、指導教員との信頼関係が構築されているため、評価面で有利になるケースもあります。
一方で、大阪大学は分野によって倍率や出題傾向にばらつきがあるため、自身が志望する研究科の過去の入試情報を綿密に分析することが重要です。
単なる偏差値の高さではなく、個別対応力と情報収集力が問われる大学院といえるでしょう。
名古屋大学大学院の合格率を探る
名古屋大学大学院は、旧帝大の一つとして高い研究評価を誇っていますが、実際の合格率は専攻や研究科によって大きく異なります。
文系では合格率が低めである一方、理系では比較的高めに推移している傾向が見られます。
例えば、理学・工学系の専攻では、研究テーマに合致している志望者であれば合格の可能性が高まります。
特に、大学側が積極的に研究室配属を進めている分野では、受験者数に対して合格者数が多く、合格率は上がる傾向にあります。
反対に、人文系や社会科学系の研究科では、定員が少ない上に志望者の質も高いため、合格率は低くなることがあります。
また、名古屋大学では、推薦入試やAO入試なども活用されており、入試方式によっても合格率に差があります。
推薦入試では成績優秀者が優先的に選抜されるため、一般入試よりも合格率は高くなる傾向があります。
このように、名古屋大学大学院の合格率を読み解くには、表面的な数字だけでなく、専攻分野、入試方式、内部進学と外部進学の割合といった複合的な要因を踏まえることが大切です。
大学院入試の難易度を見極める指標

大学院の入試難易度は、単に大学の名前や偏差値だけでは判断できません。
志望者数や倍率、研究分野の特性、入試方式の違いなど、複数の要素が絡み合って難易度は決まります。
ここでは、大学院入試の「難しさ」を見極めるために押さえておきたい重要な指標や情報収集のポイントを解説します。
受験戦略を立てるうえで知っておきたい実践的な視点を紹介していきますので、志望校選びに役立ててください。
東北大学大学院の入試情報
東北大学大学院は、東日本を代表する研究機関として、国内外から高い評価を受けています。
入試制度は研究科ごとに異なるものの、基本的には筆記試験、研究計画書の提出、面接がセットで実施されることが多く、学力だけでなく研究への適性も重視される傾向があります。
また、同大学院ではTOEICやTOEFLなどのスコア提出を求めるケースも多く、英語力も評価対象として見られる点には注意が必要です。
特に理系の専攻では、研究において英語文献の読解力が必須とされるため、受験前から英語の基礎力をしっかり身につけておくと安心です。
東北大学の入試情報は、比較的早い段階で公式サイト上に詳細が公開されるため、募集要項をよく確認し、出願準備を計画的に進めることが重要です。
なお、研究室によっては出願前に教員との面談が必要な場合もあるため、事前に連絡を取ることを強く推奨します。
全体として、東北大学大学院は難易度が高すぎるわけではありませんが、油断できる内容でもなく、バランスの取れた入試対策が求められます。
九州大学大学院は入りやすい?
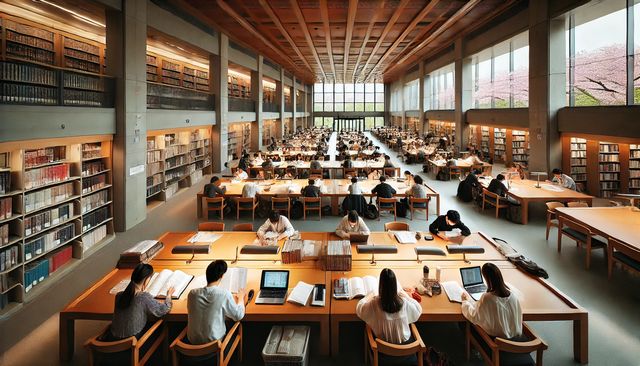
九州大学大学院は、全国的な知名度と評価を誇りながらも、入試のハードルは研究科や専攻によって大きく異なります。
一見すると旧帝大ということで難関に思えるかもしれませんが、実際には比較的入りやすい分野も存在しています。
特に、理系の一部専攻では受験者数が定員を下回ることもあり、条件を満たしていれば合格できる可能性は十分にあります。
ただし、これはあくまで一部の話であり、人気の高い専攻や文系の研究科では依然として競争率が高めに推移しています。
また、内部進学者と外部受験者の合格率にも差が出ることがあり、内部生は日常的に研究室との関係を築いているため、研究計画書の内容や面接での評価が有利になることがあります。
このように、九州大学大学院の「入りやすさ」は一律ではありません。
志望する分野の過去の倍率や入試内容を調べ、研究室とのマッチングを重視した準備を進めることが大切です。
早めの情報収集が、合格への近道となります。
北大大学院の難易度レベルとは
北海道大学大学院(通称:北大大学院)は、自然科学・農学・工学など幅広い分野で実績のある研究機関であり、その入試の難易度も分野によって大きく異なります。
全体的に見ると、旧帝大としてはやや落ち着いた倍率の専攻も多く、適切な対策を行えば合格の可能性は十分にあります。
一方で、環境科学や獣医学といった特色ある専攻では、志望者が集まりやすく、専門性の高さからも入試の難易度が上がる傾向があります。
また、北大の大学院は「研究との適合性」を重視するスタンスを持っており、研究計画書の内容がどれだけ指導教員の専門分野と一致しているかが、合否を大きく左右します。
加えて、北海道という地域性もあり、進学前にキャンパスへ訪問する学生はやや少なめですが、可能であれば研究室訪問やメールでの事前相談をしておくことで、準備不足を防ぐことができます。
北大大学院は、極端に難関という印象はないものの、「誰でも簡単に入れる」というわけではありません。
志望理由の明確化と計画的な対策が、合格を掴むカギとなります。
東工大大学院の倍率と対策
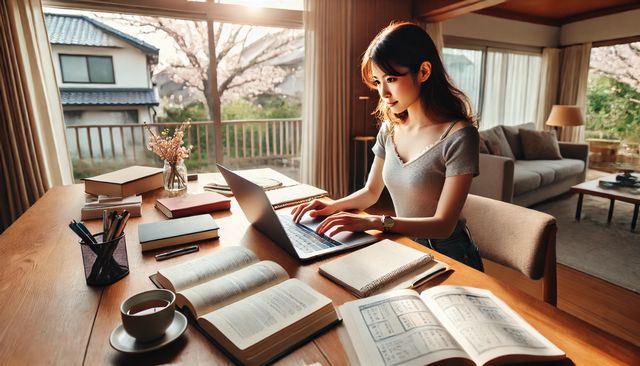
東京工業大学大学院(東工大大学院)は、理工系に特化した国内有数の研究機関であり、その入試倍率は研究科や専攻によって幅があります。
全体としては1.5から2.5倍程度の倍率が多いものの、先端技術系や人気のAI・データサイエンス系では、さらに競争が激しくなることがあります。
東工大の大学院入試の特徴は、筆記試験の内容が高度かつ専門的であることです。
学部での学習内容をベースにしつつも、大学院レベルでの応用力が問われるため、教科書レベルの知識だけでは対応が難しい場合もあります。
過去問が一部公開されているため、それをもとに出題傾向をつかみ、弱点を重点的に補強することが有効です。
また、研究計画書の提出や面接では、受験者が自分の研究テーマについてどれだけ深く理解しているか、どのように問題意識を持っているかが問われます。
そのため、単に「テーマが決まっている」だけではなく、背景や意義、研究方法に至るまで一貫性のある構成が必要です。
さらに、東工大ではTOEFLやTOEICのスコアを英語評価に活用する研究科が多いため、英語の対策も早めに始めておくと安心です。
トータルでの準備が求められる分、入試対策には時間と労力を要しますが、その分だけ研究環境としては非常に優れた学びの場が待っています。
一橋大学大学院の入試概要
一橋大学大学院は、社会科学系の分野において国内有数の研究水準を誇る大学院です。
経済学、商学、法学、社会学などに強みを持ち、特に政策やビジネス、国際関係に興味を持つ受験者から高い人気を集めています。
入試形式は研究科によって異なるものの、多くの専攻で筆記試験、研究計画書、面接の3つを軸に選考が行われます。
筆記試験では、専門分野に関する理論的な理解が問われるだけでなく、論述問題も多く出題されるため、単なる知識の暗記では対応が難しい傾向があります。
また、英語についてはTOEFLやTOEICなどのスコア提出が必要となることが多く、これらのスコアも合否に一定の影響を与える要素です。
研究計画書では、問題設定の明確さや先行研究との関係、自身の学習計画の具体性が評価されます。
テーマがどれだけ研究的価値を持っているかだけでなく、それを一橋大学で行う必然性を示すことも大切です。
このように、一橋大学大学院の入試は、知識と論理的表現力、そして研究者としての姿勢が問われるバランス型の試験であるといえるでしょう。
早稲田大学大学院の難易度分析

早稲田大学大学院は、文系・理系問わず多様な専攻を抱えており、国内外から多くの受験者が集まります。
そのため、全体的な難易度は高めです。
ただし、専攻や入試方式によって難易度の差が大きいため、一概に「早稲田は難しい」とは言い切れません。
特にビジネスや法学、国際関係などの人気分野は志願者が集中しやすく、倍率も高めに推移する傾向があります。
一方で、社会人入試やAO入試、推薦入試といった柔軟な受験制度も整っており、出願条件を満たせば、筆記試験が免除されるケースもあります。
また、一般入試では研究計画書と面接が重視されることが多く、どれだけその専攻分野に対して明確な問題意識と解決意欲を持っているかが重要です。
単なる知識の詰め込みでは太刀打ちできず、自分の過去の経験と研究テーマをどう結びつけて語れるかが、合格への鍵となります。
難易度は決して低くありませんが、多様な入口があるのも早稲田の特徴です。
自分に合った入試方式を選ぶことで、合格の可能性を高めることができるでしょう。
中央大学大学院の特徴と合格対策
中央大学大学院は、法学やビジネス、公共政策などを中心に、実務に直結した教育と研究を提供している点が特徴です。
中でも法学研究科は、司法試験を目指す学生や法務実務者にとって人気があり、レベルの高い教育が受けられる場として知られています。
入試では一般入試のほか、社会人向けの特別選抜や自己推薦型の入試など、複数の方式が用意されています。
一般入試では筆記試験、面接、研究計画書の3つが基本であり、特に研究計画書の質が合否を左右すると言っても過言ではありません。
筆記試験は、学部レベルの基礎知識をベースとしながらも、実際の事例を分析するような応用問題も出題されるため、教科書的な理解に加えて時事問題への関心も求められます。
面接では、研究への熱意や大学院でのビジョン、将来のキャリア設計なども具体的に問われます。
合格対策としては、過去問の分析とともに、実際に大学院の説明会やオープンキャンパスに参加し、教員の方針や研究室の雰囲気を把握することが効果的です。
自分の研究テーマと大学院のリソースがどのように結びつくかを明確に説明できれば、合格への道は確実に近づきます。
【まとめ】大学院入試の難易度を理解するための総括
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。


