東京大学大学院の入試について調べていると、「東大大学院の難易度は高いのか?」「倍率や偏差値はどのくらい?」といった疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
特に、学部入試と違って情報が少ない大学院入試は、その実態が見えにくく、不安に感じることもあるかもしれません。
実は、東京大学の大学院には研究科ごとに難易度が大きく異なり、倍率が高いところもあれば、いわゆる「穴場」とされる分野も存在します。
この記事では、東大の大学院入試における偏差値という指標の有無や、実際に定員割れが起こっている研究科の事例、「誰でも入れる」と噂される根拠の検証まで、多角的に解説していきます。
さらに、理系・文系の違いやランキングに左右されない研究室の選び方、東大まちづくり大学院や医学部、看護といった注目の専攻も取り上げています。
建築の難易度や心理学の試験形式、情報 理工の出題傾向、経済学研究科の高倍率など、人気分野のポイントも詳しく紹介。
これから受験を検討する方が、正確な情報のもとで戦略を立てられるよう、わかりやすく整理しています。
■本記事のポイント
- 東大大学院の倍率や偏差値の実態
- 研究科ごとの難易度や定員割れの有無
- 穴場の専攻や人気分野の試験傾向
- 難易度だけでない研究室選びの重要性
東大大学院の難易度は本当に高いのか?

東京大学大学院と聞くだけで、誰もが「難関」「超優秀な人だけが行ける場所」といった印象を持つかもしれません。
しかし実際の難易度や入試の仕組みは、世間で思われているイメージと異なる部分もあります。
学部入試と違い、大学院には大学ごとに異なる選抜方法や基準が設けられており、偏差値だけでは測れないポイントが存在します。
この記事では、東京大学大学院に進学を考えている方、または「東大 大学院 難易度」で検索している方に向けて、倍率や偏差値、入試制度の実態、さらには「穴場」や「誰でも入れる」といった噂の真偽まで、具体的なデータと仕組みをもとにわかりやすく解説していきます。
倍率から見る東京大学大学院の実態
倍率だけを見ると、東京大学大学院は必ずしも「超難関」というわけではありません。
令和3年度のデータによると、全体の志願者数が8,126人、入学者数が3,323人であり、倍率は約2.4倍でした。
つまり、10人が受けて4人以上が合格している計算になります。
一方で、この数値はあくまで平均値です。
研究科ごとに大きなばらつきがある点には注意が必要です。
例えば、薬学系は1.2倍と比較的低いのに対し、経済学研究科は3.9倍と非常に高い倍率です。
文系は理系に比べて定員が少ない傾向があるため、倍率も高くなりやすいのです。
また、内部生と外部生でも差があります。
東大出身の学生の倍率は1.4倍ですが、他大学から受験する学生の倍率は3.4倍と、明確に異なります。
外部生にとっては情報面のハンデがあるため、事前の準備が合否に大きく影響します。
このように、東京大学大学院の倍率は一律ではなく、研究科・出身校によって難易度は大きく変動します。
数字だけに惑わされず、各専攻の実態を理解することが大切です。
偏差値という指標は大学院にあるのか?
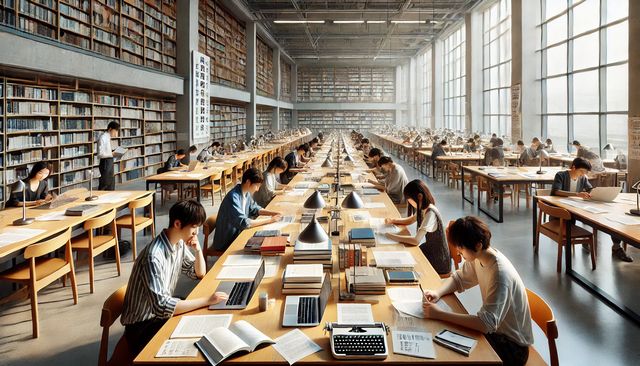
大学院入試において、「偏差値」は原則として存在しません。
これは、大学院が学部入試とはまったく異なる選抜方式を採用しているからです。
そもそも偏差値は、同一形式の全国模試などで比較可能なデータが揃って初めて成り立つ指標です。
しかし大学院入試は大学ごと、研究科ごとに独自の試験内容や評価基準を持ち、全国統一の模試などは存在しません。
そのため、東京大学大学院においても「偏差値70以上必要」といった表現は正確ではありません。
代わりに、TOEFLスコア、筆記試験、研究計画書、面接といった多角的な要素で合否が判断されます。
ただし、学部での成績や研究経験が評価されることも多いため、一定の学力や知識は当然必要になります。
特に外部進学者は、内部進学者に比べて情報不足になりやすいため、過去問や面接の準備は念入りに行う必要があります。
このように考えると、大学院入試においては「偏差値」という単純な基準よりも、自分の研究計画と熱意、試験対策の質が問われているのだと理解しておきましょう。
定員割れは起こるのか?
東京大学大学院といえど、すべての研究科・専攻で定員が埋まっているわけではありません。
実際には一部の研究科で定員割れが発生するケースもあります。
ただし、それは決して入試が易しいことを意味するわけではありません。
例えば、柏キャンパスに位置する新領域創成科学研究科などは、学部を持たないため東大生の志願者が少なく、結果として定員に満たない場合があります。
また、非常に専門性が高い分野や、知名度の低い専攻では志望者が集まりにくく、定員割れにつながることもあります。
一方で、定員割れしていても合格基準を満たさなければ不合格になることもあります。
つまり、定員割れ=入りやすいとは言い切れません。
教授陣が設定する基準を満たすことが前提です。
このように、東京大学大学院で定員割れが起こるのは事実ですが、それを理由に「簡単に入れる」と考えるのは危険です。
事前に研究科ごとの情報をしっかり調べ、学力だけでなく、研究適性も評価されることを理解しておきましょう。
穴場研究科とは?
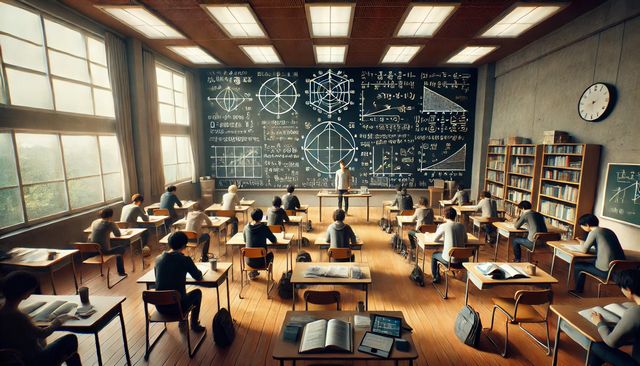
東京大学大学院の中にも、相対的に倍率が低く、いわゆる「穴場」とされる研究科があります。
代表的な例として挙げられるのは、薬学系研究科や一部の理系研究科です。
これらは倍率が1.2から1.5倍程度と、東大の中では比較的受かりやすい部類に入ります。
また、新領域創成科学研究科や情報学環・学際情報学府なども、志望者の数に対して入学枠が多く、戦略次第では外部生にもチャンスがある研究科といえるでしょう。
特に情報学環は、出願時期が年に2回あり、併願も可能なため、柔軟な受験計画が立てやすいという特徴もあります。
ただし、穴場といっても研究内容の専門性は非常に高く、志望理由や研究計画が曖昧なままでは合格できません。
形式的に受験できるからといって、興味や適性がない分野に挑戦するのはおすすめできません。
つまり、東京大学大学院の「穴場」は確かに存在しますが、事前のリサーチと自分との適合性の見極めが成功の鍵を握ります。
誰でも入れるは本当?入試の現実とは
インターネット上では、「東大の大学院は学部より簡単だから誰でも入れる」といった情報を目にすることがあります。
しかし、これは一部の情報を誇張したものであり、実態はもう少し複雑です。
確かに、大学院入試の倍率は学部入試に比べて低めで、筆記試験の科目数も少ないことが多いため、「難易度が低い」と感じられる部分もあります。
また、専門科目と英語、面接で評価されるため、対策が立てやすい点も事実です。
一方で、東京大学大学院を志望する受験生は、もともと高い学力や研究意欲を持っている層が多く集まります。
さらに、研究計画や志望動機を論理的に説明できるかどうかも重要です。
そのため、「誰でも受かる」という表現は正確ではありません。
そしてもう一つの落とし穴が、志望研究室選びの重要性です。
希望する研究室が競争率の高い人気研究室だった場合、試験の点数だけでなく、研究への適性や将来性まで評価されることになります。
つまり、東京大学大学院は誰にでも門戸を開いてはいるものの、入試を甘く見て良いというわけではありません。
しっかりと準備し、研究計画や自己分析を深めた上で挑戦することが求められます。
東大大学院ランキングと難易度の関係

東京大学大学院には、国内外で高く評価されている研究科が多数ありますが、その「ランキング」が直接的に入試の難易度を反映しているとは限りません。
大学院におけるランキングは、研究実績や論文数、教員の評価、国際的な連携などをもとに決定されることが多いため、あくまで研究内容の評価に基づいたものです。
たとえば、経済学研究科や法学政治学研究科は対外的な評価が非常に高く、研究者養成機関としての信頼も厚いですが、それゆえに志望者が集中し、倍率が高くなる傾向があります。
一方で、理工系の中には、研究環境として非常に優れていても、入試の競争率が比較的低い分野も存在します。
このため、ランキング上位だからといって必ずしも入試が難しいというわけではありません。
むしろ、研究分野のマッチングや研究室の指導方針を理解することの方が、合格に近づくカギとなります。
理系と文系の院試の難易度比較
東大大学院における理系と文系の入試難易度には、明確な差があります。
一般的に、倍率という観点から見ると文系の方が高い傾向にあります。
これは、文系研究科の定員が理系よりも少ないためです。
たとえば令和3年度の入学定員では、文系が約870人に対し、理系は2,190人と2倍以上の差があります。
また、理系ではTOEFLスコアと専門科目の筆記試験、そして研究計画の完成度が重視されます。
研究内容と指導教員のマッチングが重視されるため、計画が現実的かつ論理的であれば、外部生でも十分に合格を狙えます。
一方で文系では、筆記試験の科目数が多く、語学力(特に英語・第二外国語)も評価対象になることが一般的です。
さらに、評価の中心に卒業論文や過去の研究内容があるため、学部時代からの一貫した学習が求められます。
こうして見ると、理系は「対策しやすいが実力勝負」、文系は「長期的な準備と深い思考力」が試される入試だといえるでしょう。
東大大学院の難易度を研究科別に解説

東京大学大学院と一口に言っても、その中には多種多様な研究科や専攻が存在します。
理系・文系の違いはもちろん、倍率や試験方式、求められるスキルや適性なども大きく異なります。
中には社会人や留学生を積極的に受け入れている研究科もあり、受験生の背景によっては「狙い目」になる分野も少なくありません。
ここでは、人気研究科の難易度、出題傾向、倍率、さらには特徴的な入試制度を持つ専攻について詳しく見ていきます。
それぞれの研究科の特色を把握することで、自分に合った戦略を立てやすくなります。
東大まちづくり大学院の入試特徴と倍率
「東大まちづくり大学院」とは、正式には「新領域創成科学研究科 社会文化環境学専攻」の一部で、都市計画や環境デザイン、持続可能な地域社会の構築を専門とする分野です。
この専攻は、文系・理系の枠を超えた学際的な研究が特徴で、建築、都市計画、社会学、政策学など多様な視点が求められます。
入試は主に夏と冬の年2回行われるため、複数回の受験チャンスがある点も受験者にとっては魅力です。
ただし、受験倍率は例年2倍前後と一定の競争があります。
特に、建築や都市計画系の分野は応募者が集中しやすいため、研究テーマの独自性や社会的意義が評価される傾向があります。
また、まちづくり系の研究科では、面接でのプレゼンテーション能力やビジョンの明確さが重視されるため、自分の研究が地域社会にどう貢献するかをしっかり語れる準備が必要です。
医学部大学院の試験内容と合格基準
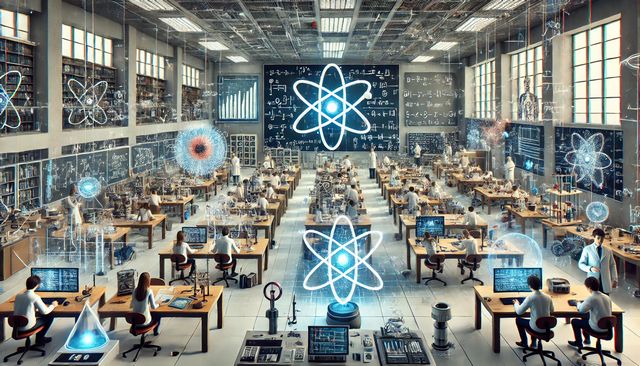
東京大学の医学系研究科は、医科学専攻、公共健康医学専攻、保健学専攻などに分かれており、それぞれに入試の特徴があります。
医師免許を持つ人向けのコースもあれば、理系出身で生命科学に興味がある人でも受験可能な専攻もあります。
筆記試験では、専門科目と英語が中心です。
特にTOEFLスコアが重視されるため、英語力の強化は避けて通れません。
医科学専攻などでは、事前に研究計画書を提出し、それに基づいて口頭試問が行われる場合もあります。
また、合格者数のデータを見ると、医学系の中でも専攻ごとに難易度が異なります。
たとえば、公共健康医学は志願者104人に対し入学者が31人と、倍率が約3.3倍とやや高めです。
医療系の研究は社会的責任が伴うため、入試では知識やスキルだけでなく、倫理観や将来のビジョンも問われる傾向があります。
単に「医療に興味がある」という理由だけでは、面接での説得力に欠ける可能性があるので注意が必要です。
看護系の入試の実態と倍率
東京大学大学院における看護系の研究科は、主に保健学専攻に含まれています。
ここでは看護学に関連した高度実践看護、看護教育、看護政策などを専門とした教育・研究が行われています。
入試では、英語(TOEFL)のスコア、専門科目、そして研究計画書の提出が求められます。
倍率については、保健学専攻全体で見た場合、令和元年度は志願者104人に対して入学者37人と、約2.8倍です。
決して低い倍率ではありませんが、適切な準備をすれば十分に突破可能な範囲です。
特徴的なのは、社会人や現役看護師が多く受験している点です。
そのため、出願時には現場経験をどう研究に活かすかが問われます。
また、保健医療における社会課題への意識が高く、研究計画にもその視点が求められる傾向があります。
入試では、実務経験と学術的な視点のバランスが求められるため、単なる経験談ではなく、明確な問題意識と研究仮説を持って臨むことが大切です。
建築の難易度は他学科とどう違うのか
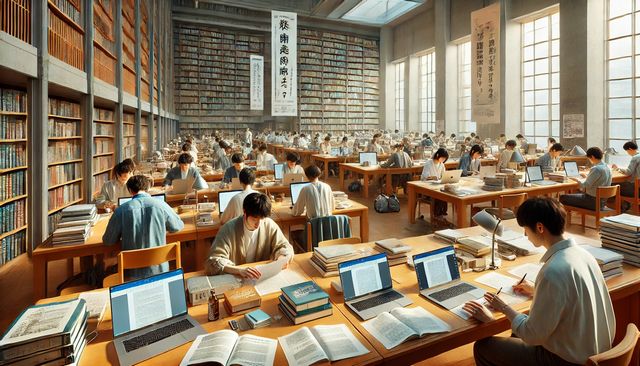
建築分野の大学院入試は、理系の中でもやや特異な位置づけにあります。
東大では、建築系は工学系研究科に属しており、都市工学や建築学の専攻として提供されています。
この分野は、数学や物理といった理系の基礎学力に加え、設計能力や空間構成力、さらには論理的なプレゼンテーション力も求められます。
これらが総合的に評価されるため、他の理系専攻とは異なる「幅広い能力」が必要とされるのが特徴です。
また、設計課題やポートフォリオの提出が求められることもあり、これは他の理工系専攻ではあまり見られない点です。
特にデザイン系の志望者にとっては、自分の作品をどれだけ論理的に説明できるかが、面接や書類選考の際に大きな鍵となります。
加えて、倍率についても専攻によってばらつきがあるため一概に語ることはできませんが、内部進学者が多い分、外部受験者は情報面で不利になることがあります。
そのため、過去問の収集やOB・OGからのアドバイスが対策として重要になるでしょう。
このように、建築分野は「理系×芸術的思考」の融合が求められる特殊な分野であり、試験対策の内容も他学科とは明確に異なります。
心理学系の難易度と試験形式の特徴
心理学を専攻とする大学院の中でも、東京大学の心理学系は非常に高い人気を誇ります。
そのため、倍率も高めに設定されており、受験対策には綿密な準備が必要です。
心理学専攻は、人文社会系研究科に所属し、文系的なアプローチに基づいて研究が行われています。
入試では、英語、専門科目、そして面接が主な選抜手段となります。
英語試験は、心理学に関する専門的な英文の読解や和訳を求められる形式が多く、日頃から専門英語に触れておくことが重要です。
専門科目については、心理学の主要分野(臨床、発達、認知、社会など)から幅広く出題されるため、偏りのない知識が必要になります。
さらに、面接では研究計画の明確さが重視されます。
心理学は臨床から実験、社会調査まで多様な研究スタイルがあるため、自分の研究テーマがその研究室の方向性に合っているかが問われます。
ここでのミスマッチは不合格の一因にもなり得ます。
心理学は学際性が高く、専門性と応用性の両方が問われるため、受験者の学習歴や問題意識の深さがそのまま評価につながります。
単に興味があるというだけでなく、「何をどのように研究したいのか」を具体的に語れる準備が不可欠です。
情報理工の東大院試対策と倍率分析
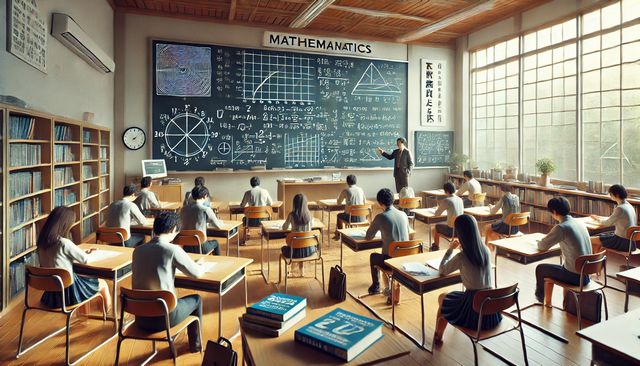
東京大学の情報理工学系研究科は、AI、データサイエンス、コンピューター科学など最先端の技術を学べる場所として国内外から注目を集めています。
受験倍率は年度によって変動がありますが、2018年度のデータでは、志願者506人に対して入学者が234人となっており、おおよそ2.2倍という数字です。
情報理工の入試では、筆記試験と英語(TOEFLスコア提出)が主な評価項目です。
専門科目では、数学(線形代数・微積分・離散数学)や情報処理の基礎、アルゴリズムやプログラミングに関する問題が出題されることが多く、他分野と比較して「理論×実用スキル」が重視されるのが特徴です。
一方で、過去問の傾向をしっかりと分析し、頻出分野に絞った学習を行うことで得点しやすいというメリットもあります。
また、TOEFLスコアが低いと合否に直結することもあるため、受験直前まで英語対策を怠らないことが求められます。
面接試験では、志望動機や研究内容だけでなく、プログラミング経験やプロジェクトベースの活動について質問されることもあります。
研究テーマと現代の技術動向をどう結びつけるかを明確にすることが、高評価につながります。
経済学系大学院の倍率と出願戦略
経済学研究科は、東京大学の中でも特に倍率が高い研究科のひとつです。
2018年度のデータでは、志願者383人に対して入学者は97人であり、倍率は約4倍に達しています。
この数値は、東大大学院全体でもトップクラスの高さです。
経済学系の入試では、筆記試験でミクロ経済学、マクロ経済学、計量経済学などが出題され、いずれも高度な数学的理解が求められます。
そのため、経済学部出身でない受験者にとっては、専門科目の対策が最大のハードルになることもあります。
加えて、英語力の証明としてTOEFLスコアの提出も必要です。
経済学の専門文献は英語で書かれていることが多いため、読解力だけでなく論理的な思考力も問われる場面が増えています。
出願戦略としては、まず志望する専攻領域に合った研究計画をしっかり練り上げることが重要です。
また、過去問の分析と模試による演習を重ね、出題傾向に慣れておくことで、着実に得点力を上げることができます。
このように、経済学系は難易度が高い分、入念な準備と専門知識の深さが求められる分野です。
単なる受験対策にとどまらず、研究者としての資質が問われると考えて臨むことが求められます。
難易度だけでない志望研究室の選び方

東大大学院を目指すうえで、「難易度」だけを基準に研究室を選ぶのは、実は非常にリスクが高い判断です。
研究室によっては、内部では「ブラック研究室」として知られている場合もあり、外部受験者にはその情報が伝わりにくいという問題があります。
例えば、研究室の雰囲気や指導スタイル、学生同士の関係性、教授の面倒見の良さといった点は、合否には直接関係ありませんが、入学後の生活満足度や研究の継続性に直結する要素です。
これを事前に把握せずに進学すると、「入ってから後悔する」ケースが少なくありません。
また、人気研究室ばかりを志望すると、受験倍率が高くなり合格の可能性が下がるという現実もあります。
反対に、希望者が比較的少ない研究室の中にも、自分の興味に合ったテーマや、将来のキャリアにつながる分野が存在することもあるのです。
そのため、研究室選びでは「どこに入りやすいか」ではなく、「どこで本当に研究したいか」「どこで長く続けられるか」を軸に考えることが大切です。
可能であれば、教授や在学生と連絡を取り、研究室見学やオンライン面談などを通じて、事前に内部の情報を得ておくと安心です。
【総括】東大大学院の難易度に関する全体のまとめ
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。


